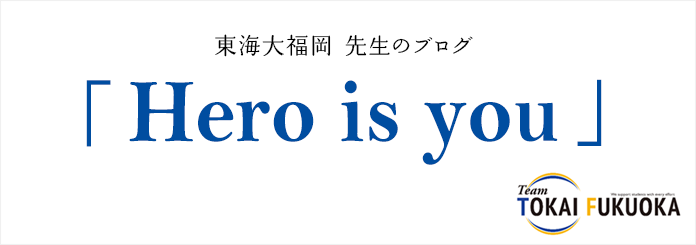

いざ大学入試センター試験!
特進主幹 岩田祐子
1990年より、国立大学の共同利用機関である大学入試センターの実施する大学入試センター試験は30年続きましたが2020年で最後の試験を迎えます。
昨年度より、次年度から始まる大学入学共通テストに関するニュースを度々目にしていることかと思います。英語の外部模試活用が延期に、そしてその後国語と数学の記述試験も実施延期となり、来年度の入試がはっきりとわからない今、今年の受験の動向も推測しかねるところもあります。予備校や塾などでは浪人を避けがちで、安定志向が強い年になりそうだという意見もありますが、とりあえずは今まで努力してきた成果を十分に発揮できることを祈ります。
さて、試験の動向もありますが、本校の3年生もこの日のために頑張ってきた人も多いのではないでしょうか。すでに緊張している人も、明日にむけて色々な考え事をしてしまうでしょうが、いつも通りに過ごすことが大切ですよ。これまで自分が頑張ってきたことがすべてだと思います。本番に実力以上の力を神頼みするのではなく、今まで自分が努力してきた力を十分に出せるよう心を落ち着けて臨んでほしいと思います。
さあ、いよいよ本番です! Do your best!

年の瀬に寄せて
教頭補佐 飯塚 浩
まもなく平成最後の年と令和最初の年が暮れようとしています。2019年の年の瀬は気温差の激しい日が繰り返され、寒暖差アレルギーという言葉もよく耳にしました。流行語は「ONE TEAM」が大賞を取り今年の一文字は「令」、東京2020の聖火リレーコースも発表されました。
マスメディアからは例年のことながら、この1年に起こった様々な事柄を振り返る情報が発信されています。これらの情報に「そうだったなー」と思いを寄せるのもよいのですが、世の中ではなく自分にとっての様々な事柄を10個挙げてみましょう。っと言われるとなかなか出てくるものではありません。自分のことを思い出すための資料を持ち合わせていますか?生徒の皆さんはポートフォリオを入力していますよね!携帯で写真を撮っていませんか?SNSで自分の情報を発信していませんか?情報化社会に生きている私たちにとって、自分の情報はしっかり整理されていないと思います。皆さんはいかがですか?
私は写真部の顧問をしておりますので、写真を添えたいと思います。上の写真は今年の1月6日に宗像市で観られた部分日食のものです。太陽を肉眼で直接見ると、失明など重大な視力障害を起こす危険性がありますので、日食専用のグラスなどを用いて安全な方法で観察する必要があります。今年のクリスマスの次の日、12月26日(木)にも日本全国で部分日食が見られる予定でしたが、悪天候だったためうまく見られなかったですね。このように写真も自分のひとつの情報として残していくのもいいかもしれません。
 それでは、良い年をお迎えください。
それでは、良い年をお迎えください。
2学期期末試験・3年生学年末試験を振り返って
1年10組担任 桶川律暢
1、2年生は二学期期末試験、3年生は学年末試験が終わり、2学期の成績処理を経て評価がでた。気持ちはもう冬休みに入っている生徒も多いだろう。仕事でも勉強でもON ・OFFの切り替えは必要だとすれば、試験が終わって一度OFFにしたい気持ちはよく解る。問題はいつONに戻すかだ。冬休みは夏休みと違って、世の中全体が「年末モード」になる。高校生も「生徒モード」から、家族の一員としての「家族モード」に組み込まれる。親の実家に行く。あるいはおじいちゃんやおばあちゃんが家に来る。中には年末年始に渡って家族旅行に出かける諸君もいるかもしれない。そうこうしているうちにあっという間に冬休みは終わる。ぎりぎりになって、冬休みの課題が追い付いていないことに気づく。そんな経験は痛いほど誰もがしてきた。よく「学生としての卒業は、人生のスタートである」というが、大げさに言えば、「試験の終わりは、次の勉強のスタートである」と言えるかもしれない。節目、節目の定期試験は、学習の到達度を測る区切りである。次の学習内容のスタートはもう迎えている。OFFはここまで。切り替えてスイッチをONに入れ直した諸君が、次の節目で笑うことになる。
…さて、かく言う私もここでスイッチをONにしなくては。
姉妹校 マレーシア・ベスタリ校交流事業 5回目を迎えて
ホームステイでよくある質問
国際交流委員長 早見京子
今年も11月に姉妹校マレーシア・ベスタリ高校から18人の高校生・4名の教職員を本校にお迎えして1週間の交流事業を行いました。具体的には生徒は平日は授業参加、週末はホームステイをして、先生方は基本的にホテル滞在で本校の授業見学と、各先生方による授業が実施されました。夏休み期間に本校からベスタリ校に行った生徒もいました。その生徒を中心に、多くのご家庭の協力のもと、ホームステイ事業も実施することが出来ました。ホームステイに興味はあるけれど、不安な点があるという方に5年間の本校の経験から分かったことをお伝えしたいと思います。
まず、最もよく質問されるのは「食事」についてです。宗教上の理由で、食べ物の制限があるマレーシアの生徒は多いです。事前調査シートで来日前に情報を把握することは可能ですが、実際に会ってみると違いがある場合もあります。一方でラーメンなどを楽しみにしている生徒もいるので、率直に「何が食べたい?」と聞くのは失礼ではありません。家庭での夕飯などは、一緒にスーパーに行き素材を選んだり、お好み焼きや手巻き寿司を一緒に作ったり、焼き鳥や天ぷらなど「素材がわかりやすいもの」が安心するようです。
次に、「習慣の違い」です。宗教によっては、1日のうちに礼拝を数回する生徒もいます。礼拝のために、早起きをして、ホストファミリーが驚いていたということもありますが、現在のところ本校では、この件に関しては大きなトラブルは起こっておりません。福岡県内の公共の場所では、福岡空港国際線ロビーやキャナルシティに礼拝所が設置されていますが、オリンピックを前に日本を訪れる外国の方も増えているので今後はさらに礼拝所も増えていくでしょう。
最後に「言葉」についてです。「子どもは簡単な英語が出来るけど、私は英語がダメで・・」とおっしゃる保護者の方がいらっしゃいますが、心配はご無用だと思います。翻訳機やスマートフォンのアプリを上手に使って、生徒たちは困ったときはコミュニケーションを取っているようです。また、お互い仲良くなると単語を繰り返し言うことで、理解し合ったりしています。もちろん、体調不良などの場合に備えて、本校内の緊急連絡先や福岡県の外国語による医療情報が得られるサイトなども、ホストファミリー事前説明会でご案内しております。
本校の国際交流プログラムを通じて、日本のことを改めて考えるきっかけになった生徒も多いようです。昭和・平成の時代よりもさらに、今後は自分と違う文化や考え方を尊重しつつ、海外の方と物怖じせずにコミュニケーションがとれる若者が増えていくことでしょう。
2019年度けやき祭を終えて
生徒会担当 : 弘中 健治
10月31日(木)、無事に本イベントを終えることができました。ご来校いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。また、ご協力いただいた保護者の方、本校関係者の皆様に感謝いたします。今年度の芸術鑑賞にも本校卒業生が出演していただきました。1人目はカラリズムリサさん。ダンスと絵画の融合はとても新鮮でした。2人目はチキンナゲッツのボーカル藤本成史さん。5人構成のバンドで出演いただき、歌っていただきました。生徒たちにとって普段の学校生活において味わったことのない、とても大きな感動を与えてくれたものでした。
この芸術鑑賞での勢いに加速され、1年生の合唱コンクール、ブラス・チアリーディング・ダンスの披露、当日の企画出展・3年生の模擬店と全ての企画に大きな活気があったと思います。とても有意義な2日間でした。最後に表彰された団体を記して終わりたいと思います。
〇1年生クラス別合唱コンクール
1位:3組 2位:10組 3位:1組 4位:4組 5位:5組
〇3年生模擬店おもてなし部門最優秀賞
3年10組
〇クラス旗部門最優秀賞
3年2組
〇クラス展示部門最優秀賞
1年9組
〇クラブ・委員会展示部門
保健委員会
〇ブロック対抗歌合戦最優秀賞
青団
「わかるから楽しい」 授業改革としてのアクティブラーニング
教務主任 田 中 明 人
昨年から始まったアクティブラーニング授業。それぞれの生徒が主体的な学びのスタイルを構築するために、脳動的な授業を行うことを目指しています。先日、行われた校内の研究授業では、それぞれの教科が、その特性を活かして授業を行っていました。また、ICTの使い方も様々で、授業を参観した教員も刺激になりました。
どんな生徒も向上したい気持ちはあると思います。わからなかったことがわかったり、出来なかったことが出来るようになることはうれしいことです。アクティブラーニングの授業では生徒の「なぜ」を大切にしています。一方的に知識を注入するのではなく、個人・集団で学習活動をしながら、「なぜ」を明らかにしていく授業は学ぶ意欲を向上させます。表情も生き生きしています。
「学ぶということは、何かが変わることだ」という言葉を聞いたことがあります。僅か50分という時間の中で、アクティブラーニングを通して生徒の何かが変わるということは、明らかに学んだ瞬間でもあると思います。
抽象的な文章になってしまいましたが、これからも私たちはアクティブラーニングやICTを活かして、「分かるから、楽しい」授業を構築していきたいと思っています。
現在、5名の教育実習生が訪れています。5名とも本校の卒業生です!
その様子を本人たちのコメントとともにご紹介します!
1週間が終わり、授業の難しさやコミュニケーションの取り方など、多くの課題が見えました。特に授業ではどのようにして生徒に興味を持ってもらうかなど、考えることが非常に多いです。残り2週間ですが、担当の先生のもとでたくさんのことを学び、いろいろな先生の授業を見学することで一つでも多くのことを吸収し、自分のものにしていきたいと思います。
有田 尚志 実習生
教育実習1週目が終わりました。この1週間で多くのことを学ぶことができました。初めて、人に対して教えるということをしました。そのことがどれだけ難しいかということに気づき、また教えている立場なのに生徒から多くのことを学べた1週間だったと思っています。そして、実際に授業の内容に関しても、課題が多く出た1週間でした。今週に出た課題を来週の授業には修正していきたいです。
津山 翼 実習生
初めてだらけのことで、色々大変だったけど、担当の先生をはじめたくさんの先生方に助けていただき、1週間乗り越えることができました。授業の方は1回1回で修正点が出てくるので、それを改善しての繰り返しで先生方の大変さを改めて感じました。1週間の反省を活かしながらもっと生徒とコミュニケーションをとりながら頑張ります。
谷光 環奈 実習生
教育実習1週間目が終わりました。人生で初めて教壇に立ち授業を行ってみて、教員という職業の難しさや凄みを肌で感じました。時間配分や板書、授業中の雰囲気作りなど、多くのことを考えて授業に臨まないといけないことに非常に苦戦した1週間でした。また、自分の高校時代を思い出し、当時の先生方にどれだけ迷惑をかけていたか痛感しました。様々なことを感じ、苦労した1週間だったので来週は今週より先生らしく頑張ります。
江崎 響太朗 実習生
教育実習の最初の1週間を終えて先生のすごさを感じたし、勉強させていただくことがたくさんあった。生徒やクラスの雰囲気、特徴を踏まえて授業を展開していくこと、常にどうすれば安全に授業ができるかを考えていることを肌で感じることができたし、その難しさも感じた。少しずつ慣れていくなかで残りの2週間でもっと色々なことを勉強し、吸収していきたいと思う。
鈴木 透 実習生
保健室の役割は生徒にとって様々です。体調不良やケガに対する応急処置としての場、身長や体重などを測定する身体測定の場、今抱えている悩みなどを相談する相談の場、学校保険の手続きの場、その他、困ったことがあったらとりあえず行ってみる場の生徒もいるかもしれません。毎日様々な理由で生徒たちはここに訪れます。
そんな彼らに保健室のイメージを聞いてみました。「心が落ち着く」「静かで穏やか」「明るい」そういった答えが返ってきました。またある生徒は「静かな楽園」とも言いました。確かに教室とは違った空気が流れています。観葉植物があり穏やかなBGMが流れる明るい場所。教室にいる時の緊張がほぐれ、ほっとするような居心地になるのかもしれません。
今生徒たちは高校生という多感な時期を過ごしています。悩み苦しむこともたくさんあるでしょう。どうしていいかわからなくなることもたくさんあるでしょう。そういった時、保健室の存在を思い出してほしいと思います。できる限り生徒の話しを聞き支援をしたいと思っています。高校時代に苦難を乗り越えることが自分自身の成長につながります。3年間という限られた時間で大きく成長することを保健室から願っています。
『宿泊研修を終えて』
研究部主任 田代 修一
今年も4月24日から26日まで、大分県中津江村にある鯛生スポーツセンターで1年生宿泊研修を行いました。私自身この研修には3年連続の参加です。場所は同じでも生徒が変わればその空間は全く別のものになる。そんなことを改めて実感した3日間でした。
この研修の目的の一つに「集団生活を通してお互いの友情や相互理解を深める」というものがあります。福岡から離れた山奥で携帯電話も持たずに過ごす生活はこの目的に添った最高の環境でしょう。集団行動や合唱などの研修内容も申し分ありません。実際にこの研修を通してクラスの友達のことを理解できた。そう実感した人は多いと思います。しかし本当にそうでしょうか・・・。私自身はそう簡単にお互いのことを理解し合えるものではないと考えています。
例えばこの3日間の中で明るい笑顔をたくさん見ました。反対に何かに苛立って怒っていたり、悲しく泣いている顔もありました。その表情の一つ一つは確かに印象的ではあります。しかしその表情が当事者の真実を映し出しているかといえばそれはまた別の話です。何故ならば私がその時に目の当たりにした出来事は日常のワンシーンに過ぎない。そう思っているからです。シーンは日々刻々と変化します。人の気持ちも変わります。はっきりしているのは泣いている人間は今泣いている。怒っている人間は今怒っている。そのことだけでそれ以外のことはわかりません。
私は嫌いな人はいません。苦手な人もほとんどいないと思います。人の悪口を言うのも好きではないです。こう言うと「嘘をつくな」と言われそうですが多分嘘ではないと思います。時に意見が合わずにぶつかることもありますが、これもまた人生のワンシーンです。その人を嫌うというレベルのものではないと考えます。そしてこの考えは自分自身に対して「くよくよと悩む必要はない」という付加価値も与えてくれます。
393人という「出会いの奇跡」に感謝出来る心を培って欲しいと思います。
自覚と責任、そして将来の道
第2学年主任 飯島 寛輝
昨年度に引き続き、学年主任を務めることになりました。昨年は右往左往しながらの毎日で本当に周囲の先生方に助けてもらい、無事に一年間を終えることができました。一年間生徒たちとコミュニケーションをとっていく中で、感じたことが2つありました。一つ目は、夢や目標、これから先の自分の将来を見つけ出せず、迷走している生徒が数多くいること。二つ目は、自分の好きなことはするが、高校生として大切な学習成績や校則やモラルを守れず頑張れずに、疎かにしている生徒がいること。
以上、2点について一人一人がもう少し考えてほしいと切に願います。
どうですか?新年度を迎え、新しい環境の中でもう一度自分自身に矢印を向けてみて、今の自分はこれでいいのでしょうか?そういう振り返れる時間というのは刻々と短くなっていますので、この一年間を高校生らしく精一杯、走り抜けてほしいと思います。そして、自分の将来、どうしたいのか?今、何をするべきなのか?どうしなければいけないのかをしっかり模索して、この一年間が終わった頃には自分の将来の道が確立しているように少し自分自身と向き合う時間を多くしてほしいと思います。
最後に、今年は元号も変わり、新たな日本となります。そういう新しい時代を君たちは生きていかなければなりません。また、活躍していかなければなりません。しっかりと時代の最先端を生きていけるようにこの高校生活を大切に過ごして欲しいと思います。
「主人公は生徒」です!引き続きよろしくお願いします!