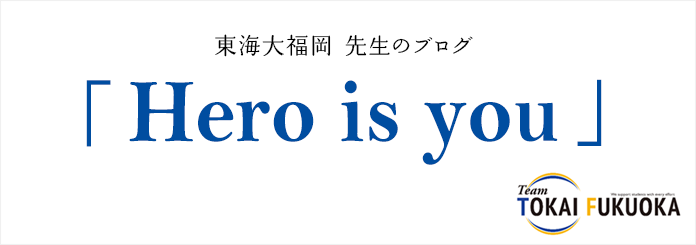
2023年度前期教育実習生より
2週間という短い期間ではありましたが、教育実習を通して、生徒の皆さんから学ぶことが多くあり、大変良い経験をさせてもらいました。多くの生徒と色んな会話ができて、記憶に残る実習となりました。ありがとうございました!
保健体育科 遠藤正景
実習を終えて、教師は多くの見えない努力があると感じました。生徒の頃は当たり前であることも教師の立場では当たり前ではなく、自分から行動し解決に向かう力はこの2週間で成長することが出来たと思います。2週間ありがとうございました。
地歴公民科 浪口真太朗
2週間の実習を終えて教師という仕事はとても忙しく大変なものだと感じました。残りの1週間はもう一段ギアを上げて楽しみたいと思います。よろしくお願いします。
保健体育科 小田晴陽
2週間実習を終えて、生徒との関わりが増え毎日の授業を楽しめています。まだまだたくさんのことを学んで吸収して、生徒と仲良くなって思い出に残る3週間にしたいです。
英語科 市山実緒
2週間終えて、生徒と一緒にお弁当を食べたり、休み時間にお話ししたりとコミュニケーションが取れて嬉しいです。1週間の元気と笑顔を忘れずに過ごしたいと思います。
英語科 花田愛海
この2週間で、先生方や生徒とコミュニケーションを沢山とり毎日1日1日を楽しく過ごすことができています。母校で実習できることに感謝し、残りの1週間頑張ります!
保健体育科 安村千奈美
教育実習を通し、改めて教員の素晴らしさを実感しました。残りの1週間で先生方や生徒からこれまで以上に多くの学びを得られるよう、精一杯頑張ります。
保健体育科 岩田春風
2週間の実習を経験し、授業の難しさを感じました。授業の何倍、何百倍もの時間を要する準備は大変で難しいです。しかし、生徒の皆さんに分かりやすいと言われることが嬉しいです。あと1週間ですがよろしくお願いします。
地歴公民科 祐野晃努
付属推薦について
進路指導部主任 福本 拡志
2023年度が始まり、2か月が経過しました。今年度より2学期制・45分7限授業・単元テストの導入など新たな変化がありましたが、学校生活には慣れたでしょうか。3年生は今月末に前期中間試験があります。希望する進路に向かって進むとても大切な試験です。良い結果が出るようにしっかりと準備をしてください。
さて、ここでは付属推薦について記載したいと思います。
付属推薦のメリットはいくつかありますが、下記のようなことが大きなメリットではないかと思います。
①6月という早期に候補者になり、残りの高校生活を好きなことに打ち込めること。
②試験は、面接がなく、小論文だけであること。
③入学金が、半額になること。
下記の表は、本校から付属推薦において、東海大学へ進学した人数と割合です。
|
年度 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
人数(人) |
59 |
57 |
69 |
63 |
77 |
60 |
|
割合(%) |
22 |
19 |
19 |
17 |
20 |
19 |
この表を見る限り、毎年20%前後の生徒が東海大学に付属推薦で進学を決めております。これは、付属高校におけるメリットを最大限活用し、自身の夢に向かって進んだ生徒の数です。
本校の生徒であれば全員に、付属推薦をすることができる権利があります。その権利を使って、大学進学を早期に確実なものとし、残りの高校生活を充実させて欲しいと考えています。そのためには、4月に実施される学園基礎学力定着度試験で良い結果を出せるように、日頃から基礎基本の学習をくり返し行うことがとても大切です。
今年度の今後の付属推薦スケジュール
|
6/15(木):付属推薦候補者発表 11/ 1(水):付属学校推薦型選抜出願受付日 11/ 8(水):学園高大連携総合試験 11/ 9(木):付属推薦「小論文」試験 12/ 1(金):付属学校推薦型選抜合格発表 付属学校推薦型選抜合格者説明会(午後)[保護者同伴] 12/16(土):付属学校推薦型選抜合格者説明会 各校舎にて |
保健室より
養護教諭 三末 詩音
新学期が始まり約2か月が経ちました。新しい学年やクラス、部活動など新しい環境や周りとの関係に慣れて学校生活も楽しくなってきたところではないでしょうか。 しかし、「5月病」という言葉があるように、環境の変化によって心と体が疲れやすくなる時季でもあります。 しっかり睡眠をとったり、ストレスを発散させたりして、自分に合った方法でうまくリフレッシュして疲れを癒してほしいと思います。
また、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の位置づけが2類から5類に移行し、3年以上にも及ぶ、新型コロナウイルスとの戦いがひとつの節目を迎えました。学校生活の中でもマスクの着用を求める必要がなくなり、コロナ前の形に戻りつつあります。しかし、コロナ自体が収束したわけではありません。咳エチケットや適切な換気、手指衛生など必要な感染対策は継続していきましょう。
みなさんの高校生活が充実したものになることを保健室から願っています。
宿泊研修を終えて
研究部主任 田代 修一
まずは4月24日からの3日間、今年も新入生宿泊研修を無事に終えることが出来たことをここに報告します。本校にとっては鯛生スポーツセンターから地元グローバルアリーナに場所を移して今回で3年目の研修でした。
私はここ数年、研究主任(副団長)という立場でこの宿泊研修に関わっています。担任は受け持っていませんが例年、研修総括としてこのブログ執筆を担当しています。実は出発前から「ある程度、このポイントで書こう」とイメージを持って現地の様子を観察していました。あらかじめイメージしておいたテーマに実際の活動を当てはめて書くといった感じの作業です。しかし今回はどういう訳か、何も浮かぶことの無いまま出発の朝を迎えました。
活動初日、生徒指導主任講話を生徒席に混じって聞いてみました。生徒目線に合わせれば少しは16歳の気持ちに近づけるかな?新しい発見があるかな?なんて考えての行動です。時には生徒の顔と名前を一致させようと無言でウロウロ歩きながらジャージのネームと顔を交互に眺める。生徒達からしたら私の行動は若干怪しく映っていたかもしれません。休憩中、べったり座り込むと隣では若い林先生がスクワット、更に体力に溢れる田中先生は空気椅子をしていました。
冒頭でグローバルアリーナにおける研修は今回で3度目と述べました。しかし実は今から15年以上前の2008年頃まで今回同様、グローバルアリーナで宿泊研修を行っていました。そこから東海大学の静岡、湘南キャンパスを巡る「未来への旅」を約5年実施、その後大分県中津江村にある鯛生スポーツセンターでの研修を経て、また戻って来たというわけです。
場所と同じく「クラス別集団行動」や「登山」など、活動内容自体も15年前と大きくは変わっていません。しかし当時を振り返った時、一つ一つの取り組み方に関しては大きな変容が見られることに気付きました。
15年以上前、まだ30代前半で担任だった頃、厳しい指導は自分の役割と言わんばかりに「動くな」、「笑うな」、「尻をはたくな」、「連帯責任、クラス全員でグランド一周」…。まさに怒号のレベルです。私のみならず全体的な風潮としてこのような雰囲気の中で進んでいくのが宿泊研修の在り方だった様な気がします。現在はというと、生徒はもちろんのこと、我々教員にも当時のような緊迫感は存在しません。集団行動の際のかけ声もみんな笑顔で活き活きと声を出します。学園体操(ラジオ体操に類似)がポップな東海福岡ダンシング(TFD)に変わり、罰則ランにしてもゲーム性を盛り込んだ延長線上にあるため、生徒自らが喜んで走っています。
そんな姿を遠目から眺めつつ、「時代の流れ」の一言で片づけてはいけないなと思いました。何故ならこれこそ本校独自のスタイルであり、掲げるスローガン「HERO IS YOU」の体現だからです。このような環境の中で生徒は物事の善悪を本質的に理解しようと努めるでしょう。また我々教員は信念に基づいて教え諭すスキルを追求します。
最後に2泊3日全体を通しての課題は3割。これこそ正に伸びしろで楽しみな要素と考えています。お読み頂きありがとうございました。
「卒業おめでとう」
3学年主任 窄朋子
卒業おめでとうございます。教室で入学式を行ってから3年。入学直後より緊急事態宣言による休校措置となり、新生活、新たな環境で新しい人間関係を構築していこうとしていたあなたの出鼻をくじく形となりました。私たち教員も初めての経験で、どのように過ごしてもらうのが1番良いのか手探りの状態でのスタートでした。それでも学校が再開してからは、学校長の判断もあり学校行事を中止することなく、コロナに対応しながら実施できたことは、高校生活の思い出としてあなたの中にたくさん残せたのではないかと思っています。
あなたが今後、新しい道に進んでいく中でこれまで経験したことがないような不条理や苦しみを感じる場面にぶち当たるかもしれません。その時にはぜひ学校へ足を運んでください。先生方が自分の考えとはまた違ったアドバイスをしてくれ視野が広がるかもしれません。たくさんの方のお力添えをいただいたおかげで今があります。人は一人では生きていけないこと、感謝することを忘れないでください。そして自分が尊敬している人と勇気を出してたくさん話をしてください。緊張してうまく想いが伝わらないかもしれません。それでもいいのです。尊敬している人に話しかけられる状況が永遠に続くことはありません。ぜひ勇気を出してたくさん話をしてくださいね。その時間は間違いなくあなたの財産になります。当たり前が当たり前でなかったことはあなたも経験し十分理解していることだと思います。今を大切にすること、できる限りの力を尽くすこと。何事にも前向きに取り組むこと。今日できることを明日に延ばすことなくやりきること。大切にしなくてはならないこと(人)を大切にできる人になっていってください。
最後に、感謝の気持ちは「言わなくても伝わっているはず」ではなくて、ぜひ「言葉」にしてほしいと思っています。言葉には「言霊」「力」があります。これからのあなたの人生が彩り豊かなものになりますように。応援しています。
高校入試シーズン到来!!
生徒募集対策室室長 西村正己
いよいよ中学3年生にとって運命の時期がやってきました。
本校生徒の皆さんも3年前・2年前・1年前と通ってきた道・・・「受験」シーズンが始まりました。
皆さんにとって先日までの冬休みはどうでしたか?女子バスケットボール部の全国3位や様々なスポーツで若者の大活躍などテレビから離れられない冬休みだったのではないでしょうか。
3学期は一年間(年度)の総締めくくりの学期です。気を引き締めて新たなステージへとつながる大事な時期です。良いスタートがきれるようにしましょう。
これからの時期は、本校では中学生3年生を対象とした高校入試が3回あります。
- 1月20日(金) 専願入試
- 2月 3日(金) 前期一般入試
- 2月 11日(土) 後期一般入試
※2月18日(土)専願合格者登校日と3月18日(土)新入生登校日です。
私は、生徒募集対策室という中学生に東海大福岡高校の良さを知ってもらう部署にいます。
私にとってもこれからの3か月は、一年間の成果が試される時期になってきます。本校生徒の良さや頑張りを伝えてこられたかな、入学後の学校生活や将来について、ちゃんとビジョンを示せたかなと・・等
中学3年生は、何を思って本校の受験を希望してきているのでしょうか?
友達が受験するから、部活動で日本一になるため、東海大学に進学したいから、などその理由は様々だと思います。しかし、やはり一番は、「充実した高校生活が送れそう」や「人として成長できそう」が多いようです。
私たち教師は、その生徒や保護者からのニーズに応えられることができているだろうか。常に自問自答しています。スポーツの指導者ではなく、塾の講師ではなく、教育者として。
私たちは、東海大福岡の教員です。約100名いる教職員は「チーム」となって一人ひとりの生徒の成長をサポートしていくのが使命だと思っています。
中学生が受験してくれるかどうかの結局のところは、今いる在校生が、もっと言うと本校を選んで入学してくれた在校生がどのくらい充実した学校生活を送っているか、学校生活に満足度を持っているかに尽きると思います。そのためには、私たち教員も「進化」しなければなりません。社会に敏感になり、生徒の将来について真剣に向き合い、変わるべきことは変化していかなければなりません。
学校は楽しくないといけないと思っています。生徒一人一人が楽しい学校生活を送るために先生たちは全力でサポートします。(楽しいは楽「らく」ではありません)
「NO FUN NO SCHOOL!(楽しくなければ学校じゃない)」
寒くなってきますが、体調管理には気を付けて有意義な3学期を送ってください。そして、近い将来後輩になる中学生を温かく見守ってあげてください。
授業評価アンケートを終えて
研究部主任 田代 修一
本校が授業改革の一環として取り組んでいる授業評価アンケートも今年で6年目を迎えました。この授業評価アンケートは生徒自身が授業を受けている全教員に向けて行います。そして他校の授業評価と違う点はこの結果を公表している点かと思います。上位1名の先生をベストティーチャー、2~10位の先生方をグッドティーチャーと称して発表します。運用として、生徒は6つの質問項目に対して4段階で評価します。それをパーセンテージ化することで全教員中、自分の順位が何位かもはっきりと示されます。ちなみに6つの質問項目もここで紹介いたします。
- 始業前に教室に入り、学習環境を整えさせ、語先後礼で共に挨拶を行っていますか?
- 無気力な生徒(居眠り・私語)、等の指導を粘り強く行っていますか?
- コンピテンシー(7つの学力)を意識し、アクティブラーニングによる授業展開がなされていますか?
- 板書、PP、プリント等、理解しやすい工夫を行っていますか?
- 情熱が感じられる魅力的な授業を行っていますか?
- 来年度も受けたい、後輩に薦めたいと思う授業ですか?
今年度のベストティーチャー賞には数学科の渡邉実香先生が輝きました。渡邉先生は表彰式の際、生徒に向けた挨拶の中で「教師として一番嬉しいと思う瞬間、これは皆さんが一生懸命頑張っている姿を見られることです。これからも授業の中でそんな場面にたくさん出会えるように頑張っていきたい」と話されました。また、「授業を行うにあたって最も心掛けていることは何ですか?」の問いには「解ること」と即答されました。
先生方が生徒に寄り添いリスペクトする。その空気感に包まれる中で、生徒も先生達をリスペクトする。この先に本校が教育目標として掲げる「授業満足度日本一」が見えてくると思っています。
期末試験・卒業試験を終えて
土居弘樹
朝、車も凍るような寒い時期がやってきました。この時期になると、もう1年が終わるのかといつも感じています。それと同時に、今年もあれをやればよかった、これもやればよかったなどの後悔なども一緒に感じています。本校でも1,2年生は2学期の期末試験、そして3年生は卒業試験が終わりました。放課後居残りをして、勉強する生徒たちの姿を見て、自分自身ももっともっと勉強をしておけばよかったなと感じさせられます。また、その姿を見て勇気、元気をもらうことができています。テスト返却も終えたいま、高校生たちの中でも、「勉強しておけばよかった〜」という声もちらほら見受けられます。この結果を踏まえて三者面談もございます。
しかし、みなさんはまだまだ若い!大切なのはこれからの行動です。これからの行動でいくらでも良い結果に変えることができます!高校生という時間はもう一生、返ってくることはありません。常に自分を見つめ、今を全力で生き、後悔のない高校生活にしてほしいと思います。また勉強だけではなく、月末には全国大会に出場する部活もあります。女子バスケットボール部、女子サッカー部です。両部活とも全国大会で上位に入る実力を兼ね備えています。ぜひ応援のほど何卒よろしくお願いいたします。
国際交流も先駆け
英語科 砂川 禎夫
このブログの閲覧されている皆様、東海大学のスローガンをご存じですか? 学園のスローガンは「先駆けであること 〜Think Ahead, Act for Humanity〜」このスローガンと交えつつ、今回の短期留学プログラムについてお話したいと思います。
今回、3年ぶりとなるマレーシアの姉妹校であるベスタリ校との現地交流が7月21日~7月28日にかけて実施されました。コロナ禍ではずっとオンライン交流は県内でも先駆けて実施しており、また現地校へ赴き、生の国際交流を実施するということも県内では本校が先駆けとなりました。コロナ禍で海外という不安な要素も大きくある中、この交流が成功したのも、姉妹校提携を結んでから約7年もの間培われてきたベスタリ校のホスピタリティ精神、そして、両校の交流に対する絆があったからこそ他校に先駆けた短期留学プログラムの実施に繋がったことかと思います。
私自身、ベスタリ校への引率は2回目で、6年ぶりとなる引率となりました。プログラムの内容は、現地校の授業に加えて、毎年変化する様々なアクティビティがあります。1年生で参加しても、また翌年参加しても異なるアクティビティがプログラムには組み込まれており、毎年異なる体験をすることができるのもこのベスタリ校との交流プログラムになっています。現地では、バディが組まれており、サポートも充実しています。今年度は、SDGsにも絡んでいる植林プログラムや現地の食を作って体験するプログラム、また伝統音楽を学ぶプログラムなど様々要素が入った交流となりました。最初は、生徒たちもワクワクする気持ちと不安が交錯する中、福岡空港での集合になりました。多くの生徒と一緒に現地で生活していると表情が研修を重ねるごとに変化しており、主体性を持ってこのプログラムに取り組む姿勢と、そして、海外文化1つ1つを胸に刻んでゆく姿が印象的でした。その中でも、私の胸に残った生徒の言葉を紹介したいと思います。福岡に帰る便でチャンギ空港での会話で「この研修中、なんか夢の中にずっといるみたいでした。」というコメントが心に残りました。この言葉が出てくるのは、言葉では表現しきれないものであり、1日1日が充実して、そして、この研修で異文化に触れ、たくさん学び、ベスタリの生徒とともに素晴らしい交流ができたからこそ出てきた言葉だと感じます。私もその言葉について、離れていくシンガポールの夜景を見ながら、「海外へ行っていたんだ。」と自分自身も実感するとともに、コロナ禍で中断していた現地での交流、海外生活やベスタリ校の生徒たちとの触れ合い、海外へ行くことの素晴らしさを再認識できる旅となりました。本校での国際交流プログラムはまだまだ再スタートを切ったばかりです。11月には、ベスタリ校の生徒を迎えるにあたり、福岡の地から国際感覚を身に付けるチャンスが広がっています。是非この機会に多くの生徒に、交流をして、自身の成長に繋げて、そして来年には多くの生徒たちがチーム東海として、先駆けとなり海外へ飛び立ち、自身の成長に繋がる活動をしてほしいです。活動の詳細は是非本校インスタグラムの様子をご覧ください。
今年度教育実習生(前期)の先生方にもブログを担当していただきました。
今回の更新は4名の先生方です。
「教育実習の意気込み」
濵野 祐貴也(担当教科:理科)
私は、本校にて教育実習を受けさせて頂く事を誠にありがたく思います。
私が教職を目指した動機は、2つあります。まず1つ目は、本校の先生方との出会いです。私は、本校に在籍していた際に進路指導や学問、部活動などの場面で多くの先生方にお世話になりました。私は、その際にお世話になった先生方と同じように生徒を支えられる仕事に就きたいと考えました。2つ目は、教師という立場への憧れです。私は、よく友達に質問をされていたのですが、説明が下手でとても時間がかかっていました。そんな時に、いつも質問すると端的に分かりやすく説明できている教師の凄さに気づきました。私もあんな風に誰が聞いても理解できる指導をしてみたいと憧れました。
私は、教育実習を通して現場の緊張感、問題が生じた際の対応力、学力にばらつきがある生徒に向けた指導方法について見学し実際に自ら行う事で身につけたいと考えています。その他にも教育実習では、授業を行う際に重要な生徒とのコミュニケーションを普段どのような感じで生徒と打ち解けられるように工夫をしているのかを学びたいと考えています。また、生徒と積極的にコミュニケーションをとり私なりのコミュニケーション方法を身につけたいです。お世話になります先生方には、尊敬と感謝の気持ちを常に持ち、教育実習を受けさせて頂く事は当たり前ではなく感謝するべき事なのだと常に思いながら自分のためになる教育実習を心掛けたいです。教育実習生としてではなく教師として常に生徒の事を第一に考え、自分の現状に満足するのではなく毎日を振り返り、反省しながらより良くなるように日々精進したいと考えています。
3週間、自分ができる事を考え、全力で頑張ります。よろしくお願いします。
教育実習を振り返って
阿部 美桜里(担当教科:国語)
初めに、お忙しい中教育実習の機会を与えて頂きありがとうございました。たくさんの先生方、生徒、そして6人の教育実習生からたくさんのことを学び、充実した3週間を過ごすことができました。まず先生方からは、授業の準備や構成から、生徒への接し方や発問の方法まで多くのことを吸収させていただきました。さらに、生徒のことを第一に考え、寄り添う姿勢というものも学ばせていただきました。
次に、生徒達は毎日、明るく挨拶をしてくれて、勉強にも部活にも一生懸命取り組む姿を見てとても励まされました。また、6人の教育実習生が努力する姿を見て学ぶことがたくさんありましたし、一緒に実習ができたことに本当に感謝しています。
最後に私自身、教えることの難しさと楽しさを感じた3週間でした。どうすれば分かりやすいのか、生徒が自ら考え、答えを導き出すことのできる授業ができるのか模索し続けました。しっかりとした答えはまだ分かりませんが、自分なりに発問や構成を工夫し実践することができたと思います。課題と反省は、これからも考え続けようと思います。
教育実習を通して出会った方々との思い出、そしてこの経験は私の宝物です。学んだことを糧に、残りの大学生活、そしてその先に活かし頑張っていきたいと思います。3週間ご指導いただき本当にありがとうございました。
大谷 未来(担当教科:保健体育)
お忙しいなか実習を受け入れてくださり、ありがとうございました。沢山の思い出が詰まった母校で教育実習を行うことができ、とても嬉しく思います。
3週間という短い期間でしたが、3年生を中心に沢山の生徒とコミュニケーションを取り、関わりを持っていくなかで、5年前では感じることの出来なかった教えることの難しさや実際に授業を行うことの難しさを実感しました。そのなかで、先生方や生徒から、授業開始の位置、指示の伝え方などの授業の中の細かい1つ1つが、生徒が取り組みやすい授業展開に繋がり生徒が授業に積極的に取り組めるようになることを学びました。
失敗も沢山ありましたが、この3週間で吸収し学んだ経験はこれから先どの道に進んでも自分の糧になっていくと思います。先生方の暖かいご指導や生徒のフレッシュな元気さで3週間やりきることが出来ました。
本当にお世話になりました。
福永 季和(担当教科:保健体育)
まずは、教育実習を受け入れていただきありがとうございます。思い出がたくさん詰まったこの東海大学付属福岡高等学校で教育実習できた事を大変嬉しく思います。
今回の教育実習で、多くのことを吸収することが出来ました。初めは、緊張や不安が多くありましたが、1日1日が濃く、毎日がとても充実していて、3週間があっという間でした。保健体育の授業の部分では、生徒が安全に楽しく授業できるように細かいところまで工夫することや生徒とのコミュニケーションの取り方、伝え方など多くのことを学ぶことが出来ました。授業以外の部分では、いろんな学年の生徒とコミュニケーションを取ることが出来ました。すれ違う時に挨拶をしてくれる生徒や、「先生!」と話しかけてくれる生徒など、たくさん生徒と関われて楽しかったです。そして、生徒が頑張っている姿を見て自分もがんばらなきゃと思えました。
この経験は一生モノで、これからの大学生活や人生に生かしていこうと思います。東海大学付属福岡高等学校の卒業生で、こんな暖かい学校で実習ができて本当に良かったです。3週間ありがとうございました。