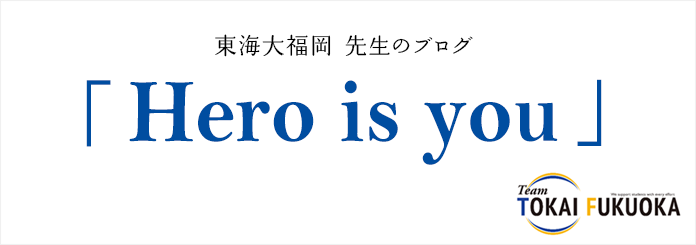
二学期末考
教務部主任 桶川律暢
二学期期末試験が終わり、職員室の先生たちは二学期の成績処理に忙しい。中間試験と違って、期末では試験を採点して生徒に返却するだけでなく、中間試験や普段の提出物等の状況を見ながら「二学期の成績」を算出しなければいけない。だからとにかく慌ただしい。学期末恒例の職場の光景だ。
学校はこの「節目」が年に3回ある。7月の1学期末と、この12月の2学期末、そして3月の学年末。この「節目」で生徒の成績や出欠席を確認し、進級や卒業が無事に出来そうか見通しを立てる。教員は自分の学習指導の成果を見せられることになるし、生徒はその学期中の自分の学習の到達度を計る。それが本来の「節目」の意味合いだろう。
自分はかつて小学校の時、終業式で通知表をもらうのが気がひけたのを思い出す。算数や理科が苦手だった私は、図工の「5」という数字が他の科目の欄にもついていたら、どんなにか胸が張れるだろうと思ったものだ。今の高校生は通知表をもらう時、どんなことを考えるのだろう。ただ担任から渡される紙切れだと思ってはいないだろうか。学期中の自分の学習を振り返り、反省する。それが詰まったのが通知表であり、それを受け取る「節目」がこの学期末だろう。それは生徒だけではない。教員もそうだ。一度、立ち止まって足元を見る。後ろも振り返る。何年も現場にいる教員ほどそれは必要なのかもしれない。
さて、温かいコーヒーでも一杯飲んでから、成績処理の続きをやるか。慌ただしい時ほど気持ちにゆとりがないと。ちょっと一息、休憩タイム。
国際交流・強化部を振り返り
教頭 山田 剛
<国際交流>
マレーシアベスタリ校との交流も4年目を迎え今年度は本校からマレーシアベスタリ校へは引率2名・生徒女子8名・男子2名が7/24~8/2の期間ベスタリ校でホームステイやアクティビティーなど充実した交流を行った。また、11/8~1/15の期間でベスタリ校から本校へ教員4名・生徒男子3名・女子15名が来校し、授業やホームステイなどで生徒や地域との交流を行い、年々充実したものになってきた。来年は交流見直しの5年目を迎えるが来年以降もより交流を深めるべく本校とベスタリ校とで交流延長が調印された。
<強化部>
毎年であるが、春から夏の大会に向けての強化計画、夏から秋・冬の大会に向けての強化計画と今年も試合の応援や大会結果に一喜一憂した一年も終わろうとしている。生徒の日々の頑張りや先生方の熱心な指導には頭が下がる思いである。昨年は夏の大会では女子サッカー・女子バスケがインターハイに出場し、冬は女子サッカー選手権出場・男子駅伝初優勝し都大路を快走した。今年は唯一全国大会へ女子サッカーが選手権に出場する。試合は年明け1月3日から始まる。悔いの残らぬよう万全な準備をして大会に臨んでほしいものである。
けやき祭そして生徒会選挙
生徒会担当 上原 洋介
東海大学湘南キャンパスには、正門から1号館に方向に約350 mの中央通りが伸びています。多くの学生が通学に利用するこの通りの脇には、数百本の欅の木が生えており、素晴らしい並木道となっています。東海大学の創立者である松前重義先生は、自身の随想集で欅の歌を詠むほど、欅の木をこよなく愛していたそうです。50年前湘南砂漠と呼ばれるほどの荒れ地に植えられた欅の木は、今や湘南キャンパスを緑に彩る大木へと成長しています。本校の校庭にも多くの欅の木が生えており、季節によって様々な色に変化しながら生徒たちを見守ってくれています。東海大福岡高校の建学祭は、その欅にちなんで「けやき祭」という名称に変わりました。3年生にとってはクラス一丸となって取り組む高校生活最後のイベント「けやき祭」。準備の段階から工夫を凝らして放課後遅くまで取り組み、当日はどのクラスの模擬店も大盛況に終わりました。前日祭には今話題のDA PUMPのパフォーマーであり、本校の卒業生でもあるKENZOさんによる講演や、ブロック対抗歌合戦など、新しい企画も行われ、大きな盛り上がりを見せた「けやき祭」となりました。
11月20日(火)は生徒会選挙が行われます。生徒会は「けやき祭」や「クラスマッチ」をはじめとする学校行事を運営し、生徒が主体的に取り組み、学校生活が充実したものとなるように企画していく役割を担っています。今回選ばれる新しい生徒会役員とともに、「主人公は生徒」のスローガンのもと、各行事を盛り上げ生徒一人ひとりが楽しめるものとしていきたいと思います。
センター試験志願! 推薦入試も動き出す
田中 明人
10月1日から大学入試センター試験の志願票の受付が始まりました。今年度は約40名がセンター試験の受験を希望しています。もちろん、私大のみの受験を希望しており、センター利用しない生徒も居りますので、実際の受験生はもっと多いのは言うまでもありません。センター試験の申し込みが終わると、いよいよ入試シーズンの開幕という感じでしょうか。
10月10日でセンター試験までちょうど100日になります。あっという間の100日。されど、100日。気持ちの変化は色々ありますが、目標に向かって地に足をつけて向かって欲しいと願っています。
また、現在は多くの生徒が推薦入試に向けて、小論文や面接などの練習に必死で取り組んでいます。それはそれで苦してこともあると思います。小論文や面接は簡単に身につくものではありません。そして、推薦入試を受験している間も、一般受験の準備を並行して行わなくてはならないのです。ある意味、正念場と言えます。それぞれの進路を掴むために、苦しいことや面倒なことにしっかり向き合って取り組んで欲しいです。
私たちも全力でサポートします。
夏も終わりいよいよ涼しい季節がやってきました。秋といえば、『食欲の秋』ですね。私も食べることが大好きで、秋が来るのを楽しみに待っていました。私が毎日利用する食堂に関して少し紹介したいと思います。本校食堂では、毎日寮生200名以上とともに、一般生徒に対しても平日、土曜日と営業しています。私も毎日食堂を利用し、生徒と一緒に食事をし、楽しい時間を過ごしております。生徒と会話をしながら食事をすることが息抜きの方法になっております。生徒に人気なメニューとして、週替わり丼のカツ丼が非常に人気があります。私も大好きなメニューの一つで、毎日食べたいと思うくらいおいしいメニューの一つです。またその他にも、週替わり定食や、牛丼、唐揚げ定食、南蛮定食、肉うどんなど子どもたちに人気のメニューがたくさん用意してあります。また、食堂にはアイスの自販機や、パンやカップ麺の販売なども行っており、小腹がすいたときなどにも利用できるようになっております。校舎内にも売店があり、パンや、ジュースなど種類豊富に揃えており、こちらも生徒だけでなく、先生にも大変人気があります。ぜひ、本校を訪れた際には食堂を利用してみてください。それでは食欲の秋を楽しみましょう。
2018年度体育祭を終えて
笠松 高志
9月7日(金)東海大福岡高校の体育祭がグローバルアリーナにて開催されました。体育祭は途中から雨天になってしまい、午前中で競技は終了して、3年生にとっては少し心残りになってしまったかもしれません。しかし、雨の中での競技でしたが生徒は必死に競技に打ち込んでいました。今回の体育祭から取り入れた各団対抗のダンスバトルでは、昨年までは女子だけが行っていた内容でしたが、男子もダンスを実施するという競技になりました。ダンス経験のない生徒が多くいる中でも、必死に踊っている姿は、新たな一面を発見でき、まとまりある内容になったと思います。また、各団発表の応援合戦では、それぞれが工夫して、生徒、保護者、教員すべての人たちを引き付ける内容であり、一生懸命になって取り組んでいる姿に多くの人が感動したと思います。
今回の体育祭は、準備の練習期間から毎日暑く、時間の確保が短いなかでありました。その中でも素晴らしかったのが、各団の団長を中心とした3年生の生徒です。体育祭を成功させようとする意識が実際の行動につながっていき、それぞれが満足いく体育祭になったと実感しています。人前に立って物事を発していき、動かすのはとても難しいことです。それを恥ずかしがることなく立派にできたことを自信として、これからの学校生活や人生に活かしてくれたと思います。
あいにくの雨により午前中で終了してしまった今年の体育祭でしたが、平日にも関わらず、多くの保護者や関係者の皆様が会場に来てくださり、本校のスローガンである「チーム東海」を感じることができました。来年度以降も素晴らしい体育祭になるように願いたいと思います。
2018年度体育祭に向けて
生徒会担当 : 弘中 健治
8月27日(月)、二学期の始業式が行われました。夏休み中に部活動の大会、国内外での様々な研修、被災地へのボランティア活動などに参加し、そのメンバーで協力して流した汗は生徒たちを成長させたと思います。生徒たちはより一層大人の顔つきになっていてとても驚かされました。
さて、二学期は“行事の学期”です。一年で一番多くのイベントがあります。その一つ目が体育祭です。今年度は新たに男女混合でブロック対抗ダンスバトルをプログラムに組み入れました。また、昨年から始まった学校応援もさらに改良してお届けします。
本番当日までもう少しです。生徒はクラスの団結はもちろん、学年の枠を超えたブロックで先輩後輩が協同し、素晴らしいチームワークを短い時間の中で培ってくれることと思います。私が担当する生徒会メンバーも一丸となり、体育祭を成功させるためにパンフレット作成や、円滑な進行を行うための資料集め、種目ごとの放送準備など生徒全員の思い出に残るイベントづくりに努力しています。生徒たちはそれぞれの役割で未来へつながる人間力を、今この時も伸ばしていてくれていることでしょう。この体育祭で更なる生徒の成長をご覧いただければ幸いです。2018年度は9月7日(金)グローバルアリーナにて9:45開始です。平日ではありますが、是非お越しください。
「在校生の頑張りをぜひ!!」
募集対策室長 西村正己
いよいよ新学期がはじまろうとしています。皆さんにとって2018年の夏休みはどうでしたか?平成最後の夏休みを充実したものにできたでしょうか?近年にない猛暑続きで大変だったと思いますが、元気な姿で新学期投稿するのを楽しみに待っています。
これからの時期は、中学生やその保護者を対象としたイベントが数多くあります。
・9月18~19日 私立高等学校「私学展」
・9月1日(土) 第1回オープンスクール
・10月6日(土) 第2回オープンスクール
・11月17日(土) 第3回オープンスクール
・12月8日(土) 入試対策説明会
など、たくさんの中学生や保護者が本校に興味を持って来校されます。
私は、生徒募集対策室という中学生に東海大福岡高校の良さを知ってもらう部署にいます。在校生の日ごろの頑張りをより多くの方に知ってもらい本校に興味関心を持ってもらうお手伝いをする部署です。
このイベントでは、本校のスローガンである「主人公は生徒(きみ)!」を軸に、様々な企画を考えております。何といっても本校の一番のストロングポイントは「生徒」だからです。
中学生やその保護者は、本校に来校する際、何を見に来ているのか?それは私の説明や施設やランチの内容より、何よりも東海大福岡の在校生の「生の姿」を見に来ています。
「学校生活は楽しそうなのかな?」
「部活の先輩は元気にしているかな?」
「ここに来たらどのような高校生活を送れるかな?」
など、在校生の素の姿を見に来ています。皆さんが3年前・2年前・1年前そうであったように、中学生は、期待と不安の中来校します。高校生となった今、皆さんができることは何でしょう?
「かしこまる」必要はありません。他と比較する必要もありません。皆さんの普段を見せてください。
学校は楽しくないといけないと思っています。生徒一人一人が楽しい学校生活を送るために先生たちは全力でサポートします。(楽しいは楽「らく」ではありません)
2学期は、体育祭・けやき祭など楽しいイベントもたくさんあります。9月初旬には「宗像フェス」にも参加します。様々なイベントや経験を通して成長した、と言える2学期にしてください。
「NO FUN NO SCHOOL!(楽しくなければ学校じゃない)」
一生に一度しかない高校生活、何事にも全力で頑張ろう!!
東海大学海洋調査研修船「望星丸」研修より 教頭 笠井 貴伸
東海大学の付属高校の魅力の一つが学園の「スケールメリット」にあります。
「東海のスケールメリット」として私が紹介したいものに「望星丸研修航海」があります。
2年に一度静岡県の駿河湾で行われる研修です。今年は7月23日(月)から25日(水)の2泊3日の研修となりました。
23日夕方静岡県清水港を出港駿河湾内のポイントを回り各種の実験を行いました。 24日にはメインの水圧実験や海底生物の採取が行われ、水深1600mの海底近くに沈めたカップ麺の容器が圧力により収縮することがわかりました。引き上げられた砂泥の中から見たこともない水棲生物が現れました。
今年度は操船体験や船の上からの夜釣りや天体観測もあり忘れられない体験となりました。
船酔いに最初は悩まされた人もいたようですがなかなかできない体験でした。
夏休みのこの時期は国際交流事業、次世代リーダー塾、学園オリンピックなど多くの研修や体験学習が準備されています。
一人でも多くの生徒が自ら手を挙げこれらの研修に積極的に参加し、様々な経験を積んで新たな夢や目標を見つけてほしいと思います。
アクティブ・ラーニング(AL)に思う
教務部主任 桶川律暢
最近、「こっそり」ハマっているのが、漢字の成り立ちを調べることだ。なぜ「こっそり」かと言うと、私は国語の教師だから。しかも教壇に立って三十数年にもなる。「え?今さらですか」と言われそうで恥ずかしいのだ。
でも、今さらでも、やっぱり漢字の成り立ちは面白い。遥か四千年もの昔に生まれたその象形は今も昔も変わらない人間のドラマを感じさせる。「愛」という字は、「頭を一生懸命巡らせる人」と「心臓」の象形から「大切にする、好きな気持ちが相手に及ぶ」意味の「愛」が生まれたとのこと。「好き」な人ができたら相手の事をたくさん知ろうとする思いは今も昔も変わらないということだろう。気になる漢字が目に入ったら、ちょっと調べてみる。自分で調べてみたことは不思議に心に残るものだ。
今、本校では「アクティブ・ラーニング(AL)」に取り組んでいる。教師からの一方向的な講義での知識の習得ではなく、生徒たちが主体的に、仲間と深く考えながら課題を解決する力を養うというのが目的だ。また、自らが進んで課題を見つけ出し、そして解決することのほうが身につくらしい。
なるほど。確かにそうだ。自分で疑問に思って調べてみた漢字の成り立ちは記憶に残る。次も調べてみたくなる。ALに取り組んでいる若い先生たちの授業を参観しながら、自分の高校時代もこんな授業だったら楽しかっただろうなと思ったりする。
勉強を怠けていた自分の責任を当時の高校の先生に転嫁してはいけないんだけどね。