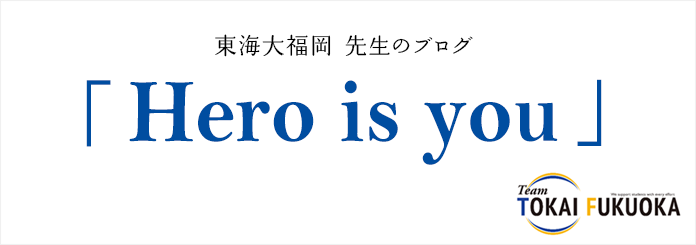
共通テストを終えて
2年9組担任 岩田 祐子
毎日、共通テストまで後何日と数え、夜遅くまで学校に残り黙々と勉強していた3年生たちが、全員無事に共通テストを受けてきました。
前日の教員たちによる激励会では、教頭先生をはじめ様々な先生より励ましの言葉をいただき、不安な気持ちを振り払って挑んでいった姿を思い出します。
共通テストの翌日も落ち着いた様子で自己採点に取り組んでいました。毎年、この結果から生徒自身が前を向いて進路のために全力をかけて取り組む姿に、私自身もすごく励まされています。進路が決まる日まで、教員一同できる限りサポートしていきたいと思います。
そして、1月30日31日には2年生が初めての共通テスト模試を受験。いよいよ自分たちが受験だ!という実感が湧いたようです。
受験生であるこの1年間で、生徒は急速に成長します。将来への不安を抱えながら一心に学習に取り組むひたむきな姿を支え見守るこの仕事がとても好きです。
3年生!2年生!そして1年生!全力で頑張れ!
授業評価アンケートより
理科 盛 一誠
今回の教職員ブログを担当します、盛と申します。よろしくお願いいたします。
2023年度の授業評価アンケートにおいて、この度グッドティーチャー賞を受賞させていただきました。私個人2021年度から3年連続の受賞になります。指導していただいた先生方、一緒になって授業をつくってくれた生徒たち、そして応援してくださった保護者の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。
振り返ると本校初任の年、高校の頃から憧れていた職業に就いた矢先に授業評価アンケートの順位がかなり下位で落ち込んでいたことを覚えています。その年に同じ理科教員の伊藤先生がベストティーチャー賞を受賞され、伊藤先生の中学校出前授業によく同行させてもらい、授業の勉強をさせていただきました。
この授業評価アンケートは、自身の立ち位置を把握し、前年度から自分がどれくらい成長をしているか認知するための大きな情報になります。また生徒は指定の項目に対してアンケートするだけでなく、自由に記述することができる欄があり、「授業がわかりやすい、おもしろい」などの言葉が返ってくると素直に嬉しいです。部活動生徒が日々の練習の成果を大会で発揮するように、教員は日々の自己研鑽を日々の授業で発揮することができ、結果が授業評価アンケートや試験結果でわかるという点で、私は教員としてのやりがいを感じることができます。
本校では今年度より全学年にiPadが支給され、先生は黒板に、生徒はノートに板書という授業風景が、先生はプロジェクターでスライドを、生徒はiPadにメモというスタイルが段々と浸透していきました。授業だけでなく採点や大学受験でもICT化が進み、益々新時代のあり方に対応していかなければなりません。我々教員も毎日学ばされることが多いと痛感させられます。
今回の結果を受けてなお、今の自身の実力に満足せず、より高い評価、より広い視野を目指して今後も教育活動に励んでいきたいと思います。
ベスタリ校歓迎プログラム 9年目の交流 「友情と学びの継続を」
国際交流委員会 早見 京子
今年度で第9回目になる国際交流事業マレーシアのベスタリ高校からの学生受け入れを11月17日~23日の期間に実施しました。プログラムは学校生活体験・ホームビジット・1日福岡市内研修などで、まだホームステイは再開していませんが、限られた日数の中でみなさん元気に過ごされました。
他校にさきがけて、2022年より対面交流を再開した本校としては、パンデミック期を経て2回目のマレーシアの高校生を日本にお招きしての交流です。生徒12名・教員3名の計15名が、来福しました。また今年は春に3か月留学生のYoung君が本校で学んでおり、例年よりもベスタリ校を身近に感じる1年だったかと思います。
初日の福岡は、小雪舞う寒さで、常夏の国マレーシアの生徒の皆さんは初めて見る雪に、曇り空を見上げ「ユキ、ガンバレ!」と歓声をあげており、車内は飛行機から降りた直後とは思えないほどエネルギーにあふれていました。
今年度の交流も全校生徒のサポート、以前本プログラムに参加したことのある生徒・卒業生、そして卒業生のご家族の方との絆を強く感じる1週間でした。今夏に現地で短期研修に参加した生徒はもちろん、特に本校に在籍するトンガ、セネガル、NZ、中国からの留学生は、ベスタリ校生徒対象の「やさしいにほんご」教室で先生役として活躍しました。
ソーシャルメディアの発展で、海外の情報が即時に入ってくる現在では、「見たことある」「知っている」レベルの情報量は10年前に比べると圧倒的に増えています。ですが、そのような時代だからこそ、勇気を出して、「直接自分が体験して学ぶ」ことの重要性は増しています。海外で起こっているニュースを学ぶことで、国際的なモラルやマナー・異文化を持つ人に不愉快な思いをさせることも減っていきます。奇しくも、ベスタリ校の国際交流事業代表のRosnah先生が「学びの重要性」について、歓迎式典でスピーチされました。その一節を引用します。
Learning knowledge is not only a duty, but also a privilege.
(学びは、学生の義務というだけではなく特権です。)
The future is unpredictable, but it is also exciting. The future is full of changes, but it is also full of possibilities. The future is shaped by the actions and decisions of people like you. The future needs people who are curious, creative, and courageous. The future needs people who have knowledge.
(未来は予測不可能です。未来は変化にあふれていますが、また可能性にも満ちています。私たちの未来は
東海生やベスタリ生のような若者にかかっています。未来は、好奇心にあふれ、創造性に富み、勇気ある人々を求めています。未来は、知識を持つ人々を必要としています。)
時代を担う東海福岡のより多くの生徒に、海外のニュースに目を向け、知識を増やし、直接に自分の出来る
形で国際交流に関わってほしいと願っています。
単なる「食べる場所」ではない食堂
食堂委員会 成井 康平
こんにちは。食堂委員会の成井です。今回の教職員ブログを担当します。
本校の食堂では寮生が朝食・昼食・夕食と、予約した通学生が昼食を食べてます。
朝食ではその日の小テストや単元テストに向けて勉強道具片手に食べていたり、昼食ではお腹をすかせた寮生が授業終了のチャイムとほぼ同時ぐらいのスピードでやってきて「こんにちは!!」と元気のいい挨拶と笑顔で食事をしています。
夕食時にはその日のエピソードトークに花を咲かせている寮生も多々見られます。
寮生の食事だけでなく、本校の食堂にはアイスやカップラーメン、パンの自販機も備わっており、放課後などもスクールバスの出発を待つ生徒たちが勉強をしたり、アイスを食べながら友達と憩いの時間を過ごしています。
私たち食堂委員は、そんな生徒たちと教職員、そして日々食事を作ってくれ、お昼には寮生に「おかえり!」と元気よく接してくれる食堂業者の方々を繋ぐ役割をしています。
食堂では前述したように生徒の様々な姿が現れます。時には食事のモラルやエチケットについての指導もすることがありますが、みんなが笑顔で過ごせる場所、単なる「食事をする場所」ではなく、人生における高校生活を支える大事な場所、そんな重要や場所に携わる責任感を持って今後とも、食堂委員一同、より良い食堂づくりに努めていきたいと思ってます。
受験シーズンに突入
3学年副主任 村上 結美
いよいよ3年生は本格的な受験シーズンに入りました。秋は行事、部活動の大会など忙しい日々を送っていましたが、その中でそれぞれの進路志望に向けて地道に受験準備を重ねていました。
そして、10月後半から12月上旬にかけては「総合型入試」「学校推薦型入試」が始まります。この入試は小論文や面接、学科試験など大学や専門学校によっても内容が異なります。だからこそ、前持った入念な準備が必要になります。
現在、3年生は休み時間や放課後の時間を使ってこの推薦入試に向けて練習を積み重ねています。また、一般入試の生徒は模試の結果が返ってきて、一喜一憂することなく来年1月の大学入学共通テスト、そしてその後の私立大学、国公立大学の入試に向けて放課後補習、土曜補習に参加し、また放課後は赤本とにらめっこしながら受験勉強を頑張っています。
卒業後の進路に向けて、私たち教員も全力でサポートしています。生徒一人一人の進路先が違うからこそ対話を重ねながら、また時には
成長するために必要なこと
生徒指導部主任 大丸 忠
「環境が整ってないから結果を出すことができない。」
こんなことをよく耳にすることがあります。
しかし、環境や誰かのせいにしている人は、環境が整っても結果を出せないことの方が多いのも事実です。
今の「自分」をつくっているのは、これまでの「自分」です。
未来の「自分」をつくるのは、これからの「自分」です。
あなたの人生の主人公は「あなた」です。
これから先の人生をより良いものにするために、人が成長するために必要なことを3点挙げてみました。
0.素直さと向上心。
|
1.自分を知る。 ↓ 2.受け入れる(自分に矢印を向ける)。 ↓ 3.飲み込み、努力する(もがく)。 成長につながるサイクル
|
前提条件として、「素直さと向上心」を挙げました。
根底に無くてはならないものとして0(ゼロ)にしています。
1.自分を知る。
評価は周囲の人がするものです。自分自身を正しく評価するのはなかなか難しい。
周囲の人からアドバイス(指摘)してもらって、今の自分の現在地を知ることは大切なことです。
2.受け入れる。
周囲からの指摘を受けて、自分自身が何を感じるか。
頑張っている人ほど、悔しさがこみあげて受け止めることができないかもしれません。
それでも、指摘してくれたことに感謝して、しっかりと受け止める(自分に矢印をむけて)ことも大切なことです。
3.飲み込み、努力する(もがく)。
様々な葛藤もあると思うが、周囲からの指摘を受け止め飲み込み、その先に良くなろうと努力する。その「もがく」作業が大切です。「もがく」作業なくして、人間的成長も目標・目的達成もありません。
繰り返しになりますが、「あなたの人生の主人公はあなたです。」
世界的な成功を収めた人でも、「最初」があります。すべては、些細なことの積み重ねです。
将来、自分がどうなりたいか「強烈な願望」(目的)を持ち続け、成長のサイクルを回してください。
そして、何事にもチャレンジしてください。
10月10日(火)福岡市総合体育館(照葉積水ハウスアリーナ)にて、スポーツフェスティバルを開催致します。スポフェスを迎えるにあたって、今回は各ブロック長の意気込みを紹介します!!
【紫ブロック】 団長:3-6立花 琉俄、山上 すみれ
今年のスポフェスは、ブロック長としてみんなの青春の思い出になるよう、一瞬一瞬を盛り上げていこうと思います。また、三年生も最後のスポフェスになるので思いっきり楽しめるよう頑張ります!!
【オレンジブロック】 団長:3-9西村 健、嶋元 梨乃亜
いよいよスポフェスが始まりますね!私たちオレンジブロックはみんなが楽しめて、笑顔溢れるブロックにしたいと思っています。私たちにとっても高校生活最後の行事なので、悔いが残らないように全力で楽しんで、最高の思い出になる行事を創り上げたいと思っています。オレンジブロック、みんなで楽しんでみんなで盛り上げていきましょう!!
【緑ブロック】 団長:3-3砂川 恵星、3-8井手口 里穂
私たち緑ブロックは、みんなが楽しく笑って過ごせるように頑張ります。ブロック長としてみんなを楽しませ、みんなで協力し合って団結力№1のブロックをつくり、優勝します!!
【赤ブロック】 団長:3-7早手 利玖、竜口 桃果
10月にスポーツフェスティバルやけやき祭が開催されることもあり、1.2年生は勉強や部活動、3年生は部活動や大学受験、就職活動等、進路選択で忙しい中、様々なイベントを迎えることになります。ですが、3年生は最後の行事なので私たちが先頭に立ち、盛り上げ、生徒だけではなく、先生や見に来て下さった人達みんなの思い出に残る最高のスポーツフェスティバルになるよう頑張ります!!
ブロック長がそれぞれの覚悟と意気込みを持って頑張りますので、全校生徒が熱く、全力で楽しめるスポフェスにしましょう!!沢山の応援、よろしくお願い致します。
今年度より生徒会を担当しています、土居と申します。よろしくお願いいたします。
さて、夏休みも終わり、本校ではこれからたくさんのイベントが待っています。スポーツフェスティバル(=体育祭 ※以下スポフェス)、けやき祭(=文化祭 ※以下けやき祭)と多くの行事が待っています。勉強も頑張りながら、高校生活でしか味わえないことや、東海大福岡の生徒じゃないと味わえないイベントがたくさん待っています。一生の思い出になるように、我々教員も力を合わせ、様々な準備を進めています。生徒の心に一生残る最高のイベントを学校で準備をしていますので、みなさん楽しみにしておいてください。
なぜ、我々教員がこれだけ行事を大事にしているのか。勉強を頑張って良い大学に進学する。もちろんこれもすばらしいことです。しかし人生において、私が思う大事なことは「経験」だと思っています。どんなことでも「経験」することが人を成長させ、心を豊かにするものだと思っています。楽しいこと、嬉しいことはもちろんですが、苦しいことも、嫌なことも「経験」することも大事なことだと思っています。嬉しいこと、楽しいことを「経験」して、感情豊かになってほしい。苦しいこと、嫌なことも「経験」し、それを乗り越え人として大きく成長してほしい。たかがスポフェス、たかがけやき祭だと思う人もいるかもしれませんが、その中には、ちょっとした経験を味わったことで、大きく成長するチャンスを手にする生徒もいると思っています。だから、我々教員は多くのイベントを用意し、最高の思い出、そして生徒のきっかけになるように教員も力を合わし頑張っています。
最高のイベント行事を東海大福岡高校は準備をしています。ぜひ楽しみにしておいてください。
在校生の頑張りをぜひ!!
生徒募集対策室室長代行 西村正己
長かった夏休みが終わり、いよいよ新学期がはじまろうとしています。皆さんにとって2023年の夏休みはどうでしたか?近年にない猛暑続きで大変だったと思いますが、夏休みを充実したものにできたでしょうか?元気な姿で登校するのを楽しみに待っています。
これからの時期は、中学生やその保護者を対象としたイベントが数多くあります。
・8月19~20日 私立高等学校「私学展」
・8月26日(土) 第1回オープンスクール
・9月30日(土) 第2回オープンスクール
・11月11日(土) 第3回オープンスクール
・12月16日(土) 入試対策説明会
など、たくさんの中学生や保護者が本校に興味を持って来校されます。
私は、生徒募集対策室という中学生に東海大福岡高校の良さを知ってもらう部署にいます。在校生の日ごろの頑張りをより多くの方に知ってもらい本校に興味関心を持ってもらうお手伝いをする部署です。
このイベントでは、本校のスローガンである「主人公は生徒(きみ)!」を軸に、様々な企画を考えております。何といっても本校の一番のストロングポイントは「生徒」だからです。中学生やその保護者は、本校に来校する際、何を見に来ているのか?それは私の説明や施設やランチの内容より、何よりも東海大福岡の在校生の「生の姿」を見に来ています。
「学校生活は楽しそうなのかな?」
「部活の先輩は元気にしているかな?」
「ここに来たらどのような高校生活を送れるかな?」
など、在校生の素の姿を見に来ています。皆さんが3年前・2年前・1年前そうであったように、中学生は、期待と不安の中来校します。高校生となった今、皆さんができることは何でしょう?「かしこまる」必要はありません。他と比較する必要もありません。皆さんの普段を見せてください。
学校は楽しくないといけないと思っています。生徒一人一人が楽しい学校生活を送るために先生たちは全力でサポートします。(楽しいは楽「らく」ではありません)9月からは、前期期末試験・スポーツフェスティバル・けやき祭など秋にふさわしい勉学や楽しいイベントもたくさんあります。11月初旬には「宗像フェス」にも参加します。様々なイベントや経験を通して成長した、と言える秋から冬にしてください。
「NO FUN NO SCHOOL!(楽しくなければ学校じゃない)」
一生に一度しかない高校生活、何事にも全力で頑張ろう!!
今年からの新たな改革!「単元テスト」について
教務主任 西村正己
生徒の「学力向上」と「定着」。
教員をしている限りこれは私たちの永遠の課題です。
この2つを確かなものにするためには,学習の定着度を細かく測るしくみが必要です。
そこで,本校では今年度より中間試験を行わず,新たに「単元テスト」を導入します。
この導入に至っては「生徒」・「教員」の双方で以下のような必要性を感じています。
・生徒たち自身が,自分の弱点に気付き,意欲をもってその克服に取り組めるようにするためには,できるだけ小さな刻みで「自分の今」を知る機会が必要である。
・教員が,生徒の弱点に気付き,必要な支援を効果的にすすめるためには,できるだけ小さな刻みで「生徒の今」を知る機会が必要である。
これまでの「定期試験」は、「課題の克服」や「学びへの意欲」,「振り返りのしやすさ」という点において,「中間試験・期末試験」はきめの細やかさに欠け,教員にとっても生徒にとっても,課題改善の材料にしにくい現状があります。
「単元テスト」に導入よる期待できることは
・生徒には,「学びやすさ」「振り返りやすさ」というメリット
・教員には,「改善へのつなげやすさ」というメリット
わたしたちは,改善のポイントの整理をとおして,内容のまとまりごとに学習と点検を行い,小さな区切りで定着の状況を測っていくことが,生徒にとっては,「学びやすさ」や「振り返りのしやすさ」に,一方,教員とっては,「課題の早期発見・早期対応」につながり,このことが学習の効果と効率の向上に有効であるとの結論に至りました。
そこで,本校では,これまで実施していた定期試験を見直し,令和5年度から以下の方法で,生徒の定着状況の把握に努めることに致しました。
・3学期制を廃止し、前期・後期の二期制とします。
・「中間試験」は実施せず,新たに全教科において「単元テスト」を実施します。
・「単元テスト」は,各教科における「内容のまとまり」や「学習の区切り」ごとに実施します(各教科年間6回程度)。
・評価の客観性をより高めるため,「単元テスト」は,教科書に準拠した一般教材を使用します。
・「期末試験」はこれまでどおり実施します。ただし,「期末テスト」は,「単元テスト」で測れなかった部分の定着度を確認するためや,「単元テスト」後の振り返りの状況を把握するための内容について取り扱います。
また,次のような点で,これまでとは異なることがあります。
・「単元テスト」には,事前の試験週間がありません。したがって,1週間前からの部活動休止期間もありません(「期末試験」には従来どおり試験週間(部活動休止期間)があります)。
生徒にとって「単元テスト」は,短期的な目標設定のもと,定期的,継続的な学習に取り組むことが可能となり,学力の定着・向上において最も重要な要素である学習習慣の定着にも効果も期待できると考えます。
7月現在、生徒の学習時間は確実に増え、学力の定着も期待できます。
この夏、長期休暇中の期間も与えあられた課題のみならず、自身のスキルアップのために様々な学びを継続してほしいと思います。
前期の期末試験は9月下旬に実施予定です。
良い準備をして、単元テストの効果を存分に発揮できるように切に願います。