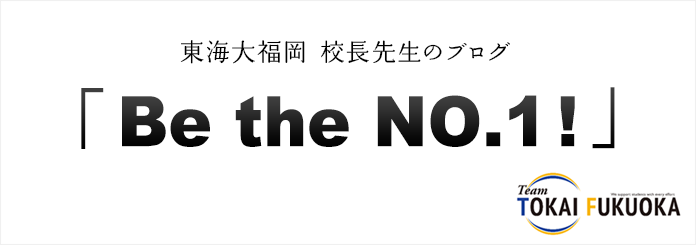
『生徒の元気な声とすてきな笑顔があってこその学校! ~感染予防意識を高く~』
昨日、3月3日から続いた臨時休校を解除し、部活動の限定的な再開をいたしました。グラウンドや体育館に生徒の元気な声とすてきな笑顔が19日ぶりに戻ってきました。思えば、この18日間、生徒の姿のない学校、生徒の声が響かない学校でありました。学校敷地内が静まりかえりまるで廃墟のような雰囲気でした。おそらく、開校以来54年間、全く生徒がいない18日間はなかったと思います。校舎もグラウンドも体育館もようやく息を吹き返して喜んでいるように見えます。本当に、生徒あっての学校だと、つくづく感じたところであります。
しかしながら、コロナウィルス感染が終息したわけでは決してありません。世界中では今も感染が拡大しております。学校にもコロナウィルスの感染が起こる可能性も否めません。我々としては、部活動の限定的な再開にあたっては、「部活動における感染予防マニュアル」を作成し、できる限りの予防対策に努めております。また、1週間再開延長しました寮につきましても、「寮生活における感染予防マニュアル」を作成し、再入寮に備えております。さらに、4月6日より迎える新学期開始にむけても「学校生活における感染予防マニュアル」を作成して、感染予防に努める所存であります。そういったマニュアルの中で一番重視していることは、自分自身の健康に常に留意して、毎日自分の健康チェックをしてほしいということです。手洗いうがいのこまめな励行はもとより朝夕の検温など、一人ひとりが感染予防に努め、自分自身の健康状況をコントロールして欲しいと思います。そのための「自己チェックシート」も準備をしています。
また、現時点では寮の再開、新学期スタートを予定通り行うように考えておりますが、国内のコロナウィルス感染について、まだまだ油断のできない状況であります。また、政府の方針や社会情勢も日々変化しています。今後、更なる臨時休校措置をとらざるを得ない状況も想定をしております。そして、もし本校の生徒や教職員にコロナウィルス感染者が発症した場合も、迅速かつ適切な対応をしていきたいと考えております。事前のお願いでありますが、その場合も、感染者に対する差別・誹謗中傷また犯人扱いなどがないようにお願いいたします。予防に努めた上での感染においては、悪いのはコロナウィルスであって、感染者ではありませんので、よろしくお願いします。
最後になりますが、一人ひとりが感染予防意識を高く保ち、チーム東海福岡として力を合わせ、コロナウィルスとの闘いに打ち勝ちましょう。なにより生徒の安全・安心を第一に学校活動を進めてまいりますので、今後ともご理解・ご協力のほど、宜しくお願いいたします。
臨時休校にあたって ~ピンチをチャンスに変えて、主体性人間になれ!~
2月27日の安倍首相による「新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休校」の要請を受けて、学校法人東海大学からの「第一段階として3月15日(日)まで臨時休校」という方針を受けて、本校でも3月2日午後より3月15日(日)まで、第一段階としての臨時休校を決めました。3月12日(木)には、臨時休業を解除するか、第二段階として臨時休校を延長するかの判断をいたします。部活動においてもその期間のすべての活動を停止といたしました。寮も留学生を除きすべて閉鎖といたしました。
このような措置はもちろん未曾有のことで、50年に一度、100年に一度の非常事態だと認識しています。生徒の皆さんには修了式でもお話しましたが、この危機すなわち「ピンチをチャンスに変えてほしい」と思っています。普段であれば授業の時間・通学に使う時間・部活動の時間、すべての時間が皆さんに与えられたということです。そのもらった多くの時間を、自分を成長させる時間にしてほしいと思っています。
学校からは、学習についての課題を提示しています。部活動によっては、日々のトレーニングメニューの指示もだされているかと思います。私は、その課題や指示にどのように取り組むのか3段階のパターンでお話したいと思います。まずは、さぼってもわからない、別に注意されるわけではない、そのうちやったらいい、って思っている人は、普段から「やらされている段階」だと思います。当然、何事もやらされてやっている状況では、自らの成長にはつながりません。次に、課題や指示されたことを自ら取り組む人は、「自主性段階」であります。真面目に課題や指示されたメニューをこなすことで、一定の成長はできることとなります。しかしながら、私が皆さんに望むことは、課題や指示されたメニューを自分なりに考えてさらに広げて取り組む人です。いわば「主体性段階」というべき人です。与えられた学習課題をさらに踏み込んで取り組む。例えば、英検対策を徹底してやるとか、スタディサプリを活用してさらに深い分野まで学習するとか、自分で自分に課すことができる人です。トレーニングメニューでも、この際自分の弱点を徹底して克服できるトレーニングを加えるとか自分なりにアレンジがすることです。こういった工夫が、自分が自分を大きく成長させるきっかけになると思っています。そして、一つの分野でもこの主体性の習慣がつけば、その人が関係するたくさんの分野にも主体的な取り組みができるようになるはずです。要するに主体性人間力が身につくということです。ぜひ、この期間に主体性人間に成長できることをめざしてください。
学校からの課題や指示以外に、この期間に取り組んでほしいことが二つあります。
ひとつ目は、この機会にたくさんの本を読んでください。普段忙しい日々を過ごしている皆さんにとっては、絶好の機会です。長編小説に挑戦するのもいい、スポーツや芸術で活躍している人を読むのもいい。本は教養をつける一番の近道です。教養はその人の品格を形成します。ぜひ、一冊でも多くの本を読んでください。そして、人生を変えるような一冊の本との出会いを経験してください。二つ目は、家族の一員としてできる手伝いをしてください。洗濯物をたたむ、食後の食器を洗う、手伝えることは一杯あると思います。こういう期間に家族の一員としての役割をしっかり果たしてください。そんな中で、家族との会話が深まるといいですね。特に寮生は家のありがたみがつくづくわかっているはずですよね。どうか、こんな時だからこそ、家族の絆を深めてください。
それでは、生徒の皆さん、くれぐれも手洗いうがいの励行など、感染予防に留意して過ごしてください。そして、ぜひ「ピンチをチャンスに変える」機会にして自分自身を主体性人間に成長させるチャンスにしてください。
また、元気に会いましょう!
卒業式 校長告辞
本日ここに東海大学付属福岡高等学校第52回卒業式を挙行できることは、誠に喜ばしいことでございます。今、呼名されました366名の卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。皆さんの入場からの様子を見ていますと、卒業式を決行することができたこと、本当に良かったと思っています。皆さんの卒業を教職員一同、心より嬉しくかつ誇らしく思っております。
保護者の皆様におかれましては、3年間本校の教育活動に対しまして、ご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございました。また、急な日程変更にもかかわらず、ご参列いただき、重ねてお礼申し上げます。本日、お子様の卒業をお迎えし、感無量の思いだと拝察いたします。誠におめでとうございます。
皆さんはこの3年間東海大福岡高校という看板を背負って頑張ってくれました。日本一の挨拶・校内外の美化活動、皆さん一人ひとりの身だしなみ、そしてなによりさわやかな笑顔。そういった小さいひとつひとつの積み重ねが東海大福岡高校の新しいイメージ・伝統になったのだと思っています。
部活動の活躍も大きな力となりました。女子バスケットボール部がウィンターカップに初出場し、新たな歴史を作ってくれました。昨年12月の終業式のとき、ここ体育館でまさに試合中のインターネット配信をスクーリーンに映して、みんなで応援したことも記憶に新しいところです。
また、女子サッカー部が昨年に引き続き、全国選手権大会に出場し、見事ベスト8となりました。昨年のベスト4には一歩届きませんでしたが、2年連続全国選手権での上位進出、全国の強豪校・常連校の地位を確かなものにしたと思います。
そして、男子剣道部が玉竜旗という全国大会で第3位という輝かしい結果を残してくれました。日々の厳しい鍛錬が全国3位というすばらしい結果に表れました。本当に全校生徒に勇気と希望を与えてくれましたと思っています。
また、文化系クラブでも吹奏楽部が一昨年九州コンクールへの出場を果たし、今年の夏も高文連全国大会出場を決めています。3年生の皆さんが、そういった出場の礎を担っていたと思っています。本当に、学校内外でめざましい活躍をしてくれました。
たくさんの部活動が、いろんなところで東海大福岡の看板と誇りを背負って、懸命に闘ってくれました。競技内容だけではなく、競技外での行動や立ち居振る舞いも大変評価されています。まさに、皆さんが、人のために体を張れる・誰かのために行動ができる人に成長をしてくれたと思っています。
さて、昨今、新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されております。未知のウイルスに個人レベルで対抗するのは、予防と免疫力だと言われています。その免疫力をあげるためには、食生活や運動、そしてストレスをためないことなどがあげられます。何より、普段の生活から免疫力を上げておくことが、大事なことだと言われています。
私が皆さんに伝えたいことは、人生においても、人生の免疫力を上げることが大事なことだということです。人生にはいろんなことが起こってきます。うまくいかない事や困難にぶち当たること、どうしようもできない悲しいことや挫折に打ちひしがれること。私は若いうちに多くの挫折を味わうことが人生の免疫力を上げることだと思っています。誤解しないでください。皆さんに挫折の人生を送れとは言っておりません。しかし、若い時、特に10代20代の時に、たくさんの挫折を経験することが、人生の免疫力を上げる唯一の方法だと思っています。人生の免疫力がないいまま40代を迎え、その時になって大きな挫折をしたら、立ち上がることは相当困難なことでしょう。若い時に、温室の内ではなく、いろんな空気に接し、人生の免疫力を上げていれば、その後の人生において未知なるできごとや、どんな困難な出来事にぶち当たっても、免疫力で乗り越えることができるはずです。
皆さんも本校での3年間のなかで、うまくいかなかったことがたくさんあったと思います。悔しくて悔しくて涙をながしたこと、たくさんあったと思います。でもそれでいいんですよ。それが皆さんの人生の免疫力になってるんですよ。これから人生で挫折したとき、きっと高校時代の経験が免疫力となってくれるはずです。
一昨日、皆さんに、たくさんの恋をしてください。という話をしましたね。皆さんのこれからの人生で素敵な恋に出逢ってください。でもね、できれば哀しい失恋・辛い失恋も味わってみなさいという話をしましたよね。ここでは言えないお話もしましたね。要するに、失恋という挫折が人生の免疫力になるということです。恋だけではありません。スポーツ、芸術、学問、いろんなことにチャレンジしてください。たくさんの目標をもち、たくさんの望みを抱き、たくさんのことに挑戦をするのです。もちろん、成功する経験もたくさん味わってほしいと思いますが、目標が達成できなかったとき、望みが挫かれたとき、挑戦に敗れたとき、そんな挫折を味わったときこそ、人生の免疫力をあげる最大のチャンスなんだと受け止めて乗り越えてください。
これからの日本社会は少子高齢化、外国人労働者とそのご家族の増加、AIやロボットの進出など、未だ日本社会として経験していないことが今後起こってくるでしょう。でも、決して負けないでください。人生の免疫力を上げて、タフな人生を力強く歩んでください。
これが、私が皆さんに伝えたい最後のメッセージです。
それでは、卒業生の皆さん、気概をもって堂々たる人生を歩んでください。皆さんの限りない前途を祝福して、私の告辞といたします。
2020年3月1日
東海大学付属福岡高等学校 校長 津山憲司
『2020年新年を迎えて』
校 長 津山 憲司
明けましておめでとうございます。皆さま方におかれましては、健やかに新年をお迎えされたこととお慶び申し上げます。
2020年(令和2年)がスタートしました。今年の干支(えと)は子年です。干支は十二支で表されており、十二支は古来より年・時刻・方位を表すのに用いられています。「子(ねずみ)」はその第一番目にあたり、時刻は午前0時、方位は北を表しています。では、なぜ「子(ねずみ)」が第一番目になったのでしょうか。こんな話が伝わっています。あるとき、神様が動物の中から12匹をそれぞれの年のリーダにすることにして、自分の家の門に早く来た順番で決めることにました。牛は動きが遅いので真っ先に出かけ、神様の家の門の前に一番に着きました。ところが、牛の頭の上に乗っていたねずみが、真っ先に門の中に飛び込んだので、子が一番になったといいます。また、猫も十二支に入れてもらおうと準備していたのですが、ねずみが集合の日をわざと一日遅れで教えたので、猫は十二支に入れなかったのです。それで、今でも猫はねずみを追い回しているということです。
さて、今年はいよいよTOKYOオリンピック・パラリンピックの年となります。どんなドラマが待ち受けているか、今から楽しみです。昨年はなんといってもラグビーワールドカップの日本代表の大活躍で、日本中が感動に湧き上がったことでした。
恥ずかしい話ですが、ラグビーに携わって40年以上の私でさえ、正直勝てるとは思っていませんでした。勝ってほしい、せめて接戦に持ち込んで欲しいとは願っていましたが、まさか本当に勝つとは信じていませんでした。自分たちよりも格上の相手に勝つことは難しいことです。チャレンジャーがチャンピオンに勝つことはあまりありません。チャンピオンが勝つことの方が圧倒的に多いのです。チャレンジャーは善戦するが、最後にはやはり負けてしまうことの方が多いのです。でも、ラグビー日本代表は、自分たちより格上のアイルランドやスコットランドに見事勝利し、目標であるベスト8に入ることができました。あきらめないで信じて努力すれば、どんな目標も達成できることを教えてくれました。だから、日本の多くの人々が感動し、勇気を与えてもらえたと思います。
ラグビー日本代表を率いたジェイミー・ジョセフヘッドコーチは、メンタル(心)の鍛え方について、「私のメンタル(心)の鍛え方は、日頃、朝起きてから“いい人格者”であること。」という言葉を残しています。メンタルの鍛え方・心の持ち方について、日頃の行動・朝起きてからの行動の積み重ねだと言っています。いかに人格を磨くか、人間力を培うかが、ここといった勝負のときにも動じない強いメンタル(心)を養う唯一の道だと解釈します。
そういえば、年末、初のウィンターカップに挑んだ女子バスケットボール部、このあと選手権大会に挑む女子サッカー部の諸君も、朝早くから人間力を磨く行動を積み重ねてくれていることは、動かざる明白な事実です。メンタルを磨く唯一の道が、日常の生活・朝起きてからのすべての行動に宿っているということを肝に銘じ、今年一年のいいスタートをきってほしいと願っています。皆さんにとってすばらしい年になることを祈念しています。
最後に、1月3日から始まる全日本高等学校女子サッカー選手権大会での活躍を期待しています。東海大福岡女子サッカー部らしいプレーをしてください。
『授業評価アンケートより』
校 長 津山 憲司
暑中お見舞い申し上げます。本日、1学期終業式を終え、いよいよ明日より夏休みに入ります。また明日は野球の試合4回戦を行われ、本校も全校応援体制で臨みます。頂点を目指し、全校生徒を甲子園まで連れて行ってほしいと思います。
さて、終業式にて1学期授業アンケート結果を発表しました。本校は、生徒の授業満足度日本一を目指しています。その実現のため、生徒の授業満足度を測る授業評価アンケートを、本校の学校改革・授業改革の重要なファクターとして、位置づけています。
今回のトップ10の先生(アイウエオ順)は、伊藤良太、今林清香、岩田祐子、笠井貴伸、笠松高志、江田一生、下園直輝、中村謙三、林紘平、松原崇志でした。10月のアンケート結果を経て、ベストティチャー候補の4名が選ばれ、グッドティチャー6名が決定することになっています。その後、4名の候補の審査授業を経て、ベストティチャーが選ばれます。
今回の全体の平均点は72.2%で、トップ10の先生の平均点は、84.4%でありました。2学期には、生徒の授業満足度が上がり、この平均点も上がるように努めたい思います。
アンケートの各項目ごとに分析すると、1項目が「学習環境整備」についてで平均79.6% 、この項目のトップは高橋文美先生で97.0%でした。2項目が「無気力な生徒への指導」については平均74.5%、トップは同じく高橋文美先生で93.9%。3項目「コンピテンシーの意識づけ」については一番低く平均62.1%、トップが笠井貴伸先生で91.0%でした。 4項目「授業内容の工夫度」については平均73.8%、トップは林英輝先生88.6%。5項目が「アクティブラーニング授業展開度」についてで平均69.5%、トップが笠井貴伸先生で85.9%。6項目が「授業の魅力度」については平均73.8%、トップは岩田祐子生先生で93.2%でした。
生徒の改善すべきコメントとしては、授業のスピードや板書についてが多かったでした。なかには、「アクティブラーニングをとりいれてほしい」「話し合いを増やしてほしい」「生徒に考えさせるような授業をしてほしい」といった本校が目指しているアクティブラーニングを柱とした生徒主体的な授業スタイルを求めるコメントも多くありました。生徒たちは本校が学校全体で授業を改善しようとしていることを感じ、わかる授業、考える授業、楽しい授業、そして積極的に参加する主体的な授業を求めてくれているということです。
授業の良いところのコメントでは、「楽しい」「毎回ワクワクして受けている」「説明が具体的でわかりやすい」「先生のおかげで教科が好きになった」「授業が明るい空気を作ってくれる」「アクティブラーニングが楽しい」「授業を改善していこうという意気が感じられる」「パワーポイントやタブレットを使ってわかりやすい」など。生徒が楽しい、わかりやすい、教科が好きになるといった授業が、やはり生徒の満足度が高い授業と言えます。
今回の生徒による授業アンケートの結果を、コメントも含め、それぞれの教員がしっかりと受けとめて、2学期に向けて授業改善に努めたいと思います。
次に、ベストクラス賞について、総合ベストクラスは1年9組でした。進学I類コースベストクラスは1年1組、進学II類コースのベストクラスは3年8組、 スーパー特進コースベストクラスが2年9組となりました。これは、全教員が自分の担当しているクラスについて、授業マナーや、授業に対する参加度・積極性、また仲間との協力度などの項目で、アンケートをとって決めます。全体の1番を総合ベストクラス。そしてそのクラスを除いて、それぞれのコースごとに学年関係なしに1番すばらしいクラス、合わせて4クラスを表彰するものです。
本校では、昨年度より身につけるべき七つの学力「コンピテンシー」を定めました。その「コンピテンシー」を身につけるための授業手法として、アクティブラーニングを推進してきました。そして、授業での10項目の約束事「Xの約束」を決めました。その「Xの約束」を基に生徒による授業評価アンケートと教師による授業クラスアンケートができています。
本校の授業は、先生と生徒が協働して創りあげるものです。東海福岡のそれぞれの授業を変化させて、東海福岡の授業全体を進化させたいと思っています。そして、東海福岡のオリジナル授業文化を構築したいと思っています。それが、これからの時代を切り拓く生徒たちの力になっていくものと信じています。
明日から夏休みに入ります。補習や部活動などそれぞれの分野で大いにチャレンジして欲しいと思います。そしてこの夏が終わった頃には逞しく成長していて欲しいと願っています。熱中症など身体に充分に気をつけて元気で夏を乗り切ってください。
皆さんのご健勝をお祈りしています。
『令和』という新たな時代へ
校 長 津山 憲司
「令和」という新しい時代がいよいよスタートしました。「初春の令月にて、気よく風和らぎ、」という万葉集の一説が典拠となった文字です。「令月」というのは、厳しい寒さに耐えて、見事に咲き誇る梅の花ように、それぞれの花を大きく咲かせる。という解釈だそうです。私は、本校のスローガンである「Be the No.1!」とよく似た解釈の漢字だと思いました。ナンバーワンをめざし、厳しさを乗り越えることで、真のオンリーワンに成長し、自分だけの美しい花を咲かせる。まさに、「令和」の「令」と同じ意味であります。そして、「令和」の「和」とは、平和の日々に心からの感謝の念を抱き、希望に満ちあふれた新しい時代を共に切り開いていく決意を表しているそうです。まさしくチーム力で新しい未来を切り開くという「Team Tokai Fukuoka!」本校のスローガンにぴったりと当てはまっています。すなわち、これから皆さんが進もうとする「令和」という時代に、本校の「Be the No.1!」「Team Tokai Fukuoka!」というスローガンは、まさに先駆けと言えます。本校は、「令和」という新しい時代を堂々と生きていく力を育てていく学校であります。
では、「令和」という新しい時代とはどんな時代でしょうか。現在の社会情勢は、SNSの普及やAI(人工知能)・ロボットなどがどんどん社会に進出してきています。また、外国人労働者とその家族とが共生できるグローバルな日本社会になることが求められています。これからの日本社会は、変化ではなく「進化」を遂げようとしているのかもしれません。
そんな進化する日本社会では、今後10年間で現在の職業の約50%がなくなると言われています。昨今のスーパーマーケットではセルフレジが着実に増えてきました。近いうちには、タクシーやトラックのドライバーが自動運転に変わり、電話のオペレータもSiriにとって代わっていくことでしょう。スポーツの分野でも、プロ野球でリクエストというVTRの判定システムやバレーボールやテニス、ラグビーでも画像での判定システムが採用されています。いづれはスポーツの審判もAIに代わっていくことになるでしょう。しかし、職業がなくなっていくことは今に始まったことではありません。30年前の職業がどう変わってきたかを考えてみると、商店は大型ショッピングセンターに、街の電気屋さんは量販店に代わってきました。以前の駅の改札では、駅員さんが切符を切っていましたが、今はどこも自動改札になっています。でも、現在でも駅には駅員さんが必要です。切符を切っていた仕事から、機械を扱って切符を発行したり、さらに高度な技術が必要な仕事や適切な接客対応が求められています。そうなんです、いつの時代でも、技術革新や社会変化で職業が消えて行ったり、また新たな職業が生まれたりしています。大事なことは、その変化に適応していく力を身につけることだと思います。
「進化論」を唱えたダーウィンの言葉に、「生き残る種とは、最も強いものではない。最も知的なものでもない。それは、変化に最もよく適応したものである。」とあります。すなわち、これからの時代で大事なことは変化に適応することであります。そして、その変化に適応するためには、自ら考え行動できる「主体的な力」を培うことだと思ってます。「主体的な力」とはなにか。それは、「自分で状況を判断して、ある目的に向かって、自ら責任をもって効果的な行動をとることができる力」のことなのです。
私は、「学校があなたに何をしてくれるのではなく、あなたが学校に何ができるのか」・「授業があなたに何をしてくれるのではなく、あなたが授業にどうかかわっていけるのか」・「チームがあなたに何をしてくれるのではなく、あなたがチームのためにどんな貢献ができるのか」ということを、深く考えてほしいと思っています。「自分が何ができる」、「自分自身」を主語にできるような主体的な考え方を持つことが肝要です。「自分が、学校に・日々の授業に・クラス活動に・クラブ活動に、そして友人や仲間に、どうかかわっていけるのか」ということを考えて、自らの行動で示してほしいと思います。皆さんにとって、日々の授業や部活動のなかで、人間力を培うという目的のために、自ら考え自ら責任をもって行動することこそが大事なことなのです。そして、「令和」という新たな時代に向かって、皆さん自身が変化に適応して「進化」を遂げ、人間力に満ちた堂々たる人生を歩んでほしいと願っています。
2019年度入学式 校長告辞
桜花爛漫、そんな言葉がピッタリとくる日になりました。先日来の花冷えの気候が幸いし、校庭の桜の花が皆様の入学を待ちわびていたように咲き誇っています。本日、ここに東海大学付属福岡高等学校 54回入学式を挙行できることは、誠に喜びにたえないところでございます。
ただいま、入学を許可いたしました、凛と目を輝かせた393名の新入生の皆さん、保護者の皆様、ご入学おめでとうございます。特に、福岡県の数ある高校から、また日本の数ある高校から、本校を進学先として選んでくれて、ありがとう。皆さんのご入学を私たち教職員一同、心より歓迎いたします。
また、校務ご多用中にもかかわらず、ご臨席いただいております、宗像市教育長の高宮様、福津市教育長の柴田様、日本赤十字九州国際看護大学の田村学長先生そして中学校の校長先生、地域コミュニティー運営協議会会長様をはじめ、多くのご来賓の皆様に、厚く御礼申し上げます。
さて、本校は東海大学の付属高校として、東海大学の建学の理念のもと、文武両道を通した人間教育に力を入れている学校です。また、本校では、皆様のお手元の入学式次第の裏表紙に載せております、スクールスローガン・スクールポリシー・そして、スクールゴールという明確な設定のもと、教育活動を展開しております。
スクールスローガンとは、本校のイメージを簡潔に言葉で表した言葉です。本校を一言で表すと、「Team Tokai Fukuoka!」、本校では、あらゆる活動をチーム力団体戦で取り組み、仲間と共に未来を切り開き、そして仲間や周りの人へ感謝の心を育てる。ひとつのチームのような学校をめざしています。二つ目は、「Be the No.1!」 厳しさを乗り越え、高い志と大きな夢に挑戦することでナンバーワンをめざし、たとえナンバーワンになれなくとも、真のオンリーワンに成長できる教育です。そして、三つ目が「The hero is you!」生徒が主人公になる活動を通して、すばらしい大人に育てる教育を展開しています。
先日、「令和」という新しい元号が発表になりました。「初春の令月にて、気よく風和らぎ、」という万葉集の一説が典拠となった文字です。「令月」というのは、厳しい寒さに耐えて、見事に咲き誇る梅の花ように、それぞれの花を大きく咲かせる。という解釈だそうです。私は、本校のスローガンである「Be the No.1!」とよく似た解釈の漢字だと思いました。ナンバーワンをめざし、厳しさを乗り越えることで、真のオンリーワンに成長し、自分だけの美しい花を咲かせる。まさに、「令和」の「令」と同じ解釈であります。そして、「令和」の「和」とは、平和の日々に心からの感謝の念を抱き、希望に満ちあふれた新しい時代を共に切り開いていく決意表しているそうです。まさしくチーム力で新しい未来を切り開くという「Team Tokai Fukuoka!」本校のスローガンにぴったりと当てはまっています。
すなわち、これから皆さんが進もうとする「令和」という時代に、本校の「Be the No.1!」「Team Tokai Fukuoka!」という考え方は、まさに先駆けと言えます。安心して本校に飛び込んできてください。「令和」という新しい時代を堂々と生きていく力を本校は必ず育てていきます。
では、「令和」という新しい時代とはどんな時代でしょうか。現在の社会情勢は、SNSの普及やAI(人工知能)・ロボットなどの社会進出によって、どんどん変化していこうとしています。いや、変化ではなく「進化」を遂げようとしているのかもしれません。そのような社会情勢のなか、私が新入生の皆さんに望むことは、「主体性」だと思っています。第35代アメリカ合衆国大統領ジョン・F・ケネディの就任演説の中で有名な一説があります。「国があなたのために何をしてくれるではなく、あなたが国のために何ができるのかを考えようではありませんか」という言葉です。
皆さんに当てはめると、「学校があなたに何をしてくれるのではなく、あなたが学校に何ができるのか」・「授業があなたに何をしてくれるのではなく、あなたが授業にどうかかわっていけるのか」・「チームがあなたに何をしてくれるのではなく、あなたがチームのためにどんな貢献ができるのか」を強く考えてほしいと思っています。「あなたが何ができる」いや「自分が何ができる」「自分自身」を主語にできるような主体的な考え方を持ってほしいと思っています。「自分が、学校に・日々の授業に・クラス活動に・クラブ活動に、そして友人や仲間に、どうかかわっていけるのか」ということを、「自分が」を主語にして高校生活大いに挑戦してください。
皆さんが主体的に挑戦する目標として、本校では三つのスクールゴールを設定しています。それは、授業 日本一、部活動 日本一、挨拶と笑顔 日本一という三つのゴールです。まずは、授業日本一とは、授業に皆さんが主体的に参加して、こんなことがわかるようになった、こんな力がついた、こんな考え方ができるようになった、という授業に対する満足度が日本一ということを目指しています。本校は部活動も盛んな学校です。いろんな部活動がめざましい成果を出してくれています。もちろん、全国制覇・日本一を果たす部活動が出てきてくれることは、大変うれしいことであります。しかしながら、本校の部活動の目的は、人間教育にあります。部活動を通して逞しい大人に育てることこそ、部活動の本当の意義です。そういった意味で、部活動日本一という目標は、部活動を通した人間教育、部活動を通した成長こそが日本一というゴールです。私は本校生徒の挨拶は日本一の挨拶であると自負しています。きちんと立ち止まって、相手にしっかり体の正面を向けての挨拶を習慣づけています。また、笑顔は内面から自然とでるもので、人を幸せにするものです。私は、本校の挨拶に心からにじみ出る笑顔が加われば、日本一の挨拶と笑顔になると思います。
このような三つのゴールを目指して、高校生活において、主体的に努力を重ねることで、どこの世界でも通用する人間力を身に付けることができます。人間力を育てることは、本校のスクールポリシーすなわち本校の教育の根本・原点であります。
そこで培った人間力は、きっと将来社会に出て、誰かの力になる、困っている人を助ける。苦しんでいる人を救う、迷っている人を導く、そういった人のために尽くすことができる人に育っていくことだと信じています。皆さんが、これから始まる高校生活のなかで、周りの人ために、仲間友人のために、誰かのために尽くしてください。それが、実は皆さん自身の力となり、皆さん自身の喜びとなり、皆さん自身の幸せにつながることとなります。どうか、人のために尽くすことが、自分の幸せと感じられる人に成長してください。
最後に、保護者の皆様、大切なお子様を、私ども東海大福岡高校にお預けいただきましたことに、心から感謝申し上げます。
私ども教職員一同は、お子様の将来への夢の実現にむけて、全力で当たる決意でございます。そして、卒業時には、すばらしい大人に成長させ、自分の夢・目標に近づく進路に繋げるため、私たち教職員一同、ひとつのチームとなって取り組んでまいります。本校は学校改革の真っ最中であります。アクティブラーニングを柱とした授業改革。挨拶・人への思いやり・マナーなどを、普通のレベルからさらにもっと高いレベルに引き上げる改革。また、教師の働き方改革や部活動改革にも着手していきます。そういった改革も、教職員と生徒そして保護者の皆様との信頼関係が肝要になると思っています。保護者の皆様には、ぜひご理解をいただき、学校を信頼していただきたいと思っております。より良い教育には保護者の皆様のご協力が不可欠であります。学校と保護者の皆様が連携をして、お子様の成長を力強く見守っていただくことを、お願いいたしまして、私の「告辞」といたします。
2019年4月6日
東海大学付属福岡高等学校 校長 津山憲司
2018年度 卒業証書授与式 校長告辞
卒業生の門出を祝うような温かい春の陽ざしが差し込んでいます。この宗像の地にも、ようやく春の訪れが感じられるようになりました。本日ここに東海大学付属福岡高等学校の第51回の卒業式を挙行できることは、誠に喜ばしいことでございます。
また、校務ご多用の中にもかかわらず、ご臨席いただいております県議会議員吉武邦彦様、宗像市教育委員会より阿部様・福津市教育員会より柴田様、そして中学校の校長先生、地域コミュニティ会長様をはじめ、多くのご来賓の皆様に、厚く御礼申し上げます。
さて、今呼名されました304名の卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。皆さんの卒業を教職員一同、心より嬉しくかつ誇らしく思っております。また、保護者の皆様におかれましては、3年間本校の教育活動に対しまして、ご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。本日、お子様の卒業をお迎えし、感無量の思いだと拝察いたします。誠におめでとうございます。
思い起こせば3年前、皆さんが本校の門戸を叩かれたときには、本校は東海大学付属第五高等学校から、東海大学付属福岡高等学校と校名変更した年でありました。いわば皆さんは、東海大福岡高校の最初の入学生であったわけです。皆さんはこの3年間新しい東海大福岡高校という看板を背負って頑張ってくれました。日本一の挨拶・校内外の美化活動、皆さん一人ひとりの身だしなみ、そしてなによりさわやかな笑顔。そういった小さいひとつひとつの積み重ねが東海大福岡高校の新しいイメージ・伝統になったのだと思います。そのお陰で、東海大福岡高校の名が地域に定着することができました。部活動の活躍も大きな力となりました。皆さんが1年生の時には野球部が32年ぶりに春の選抜甲子園に出場し、ベスト8となりました。また、2年生の時には、男子駅伝チームが、強豪伝統校を破り、初優勝し、年末の京都都大路を初めて疾走してくれました。3年生になって女子バスケット部と女子サッカー部がインターハイに出場、個人でも柔道・陸上でインターハイに出場してくれました。また、文化系クラブでも吹奏楽部が創部以来初めて九州コンクールに出場し、すばらしい演奏を奏でてくれました。そして、今年になって女子サッカー部が全日本選手権大会3位という輝かしい歴史を作ってくれました。その栄光は、様々な部活動、いやチーム東海福岡全員に大きな自信と勇気をあたえてくれました。いろんな部活動が、いろんなところで東海大福岡の看板と誇りを背負って、活躍してくれました。競技内容だけではなく、競技外での行動や立ち居振る舞いも大変評価されています。まさに、皆さんが、周りに目配り気配り心配りができる人に成長をしてくれたと思っています。
さて、皆さんが今日、本校を巣立ち、羽ばたいてむかう社会は、どんな社会でしょうか。AI人工知能やセルフレジなどのロボットが日常に加わる社会がもうすぐそこまで来ています。どうか、AIやロボットに負けないでください。どんな知能や利便性も超越する、人間力で勝負してください。本校のスクールポリシーは、「人間力を育てる」ことです。皆さんは、高校生活3年間でその人間力を培ってきたと思います。どうか、これからも、豊かな人間性を磨き、社会実践力を高め、そして、どんなことにもくじけない強い心、気概をもって、堂々たる人生を歩んでほしいと願っています。
つい先日、最後の現代文明論として、皆さんにお話しをしたこと、覚えていますか。若き日にで始まる四つの言葉の通り、皆さんのこれからの長い人生において、若いときの経験や人との関わりのなかで培ったこと、養ったこと、磨き上げたことが、自らの生き方や人生観の根本となり、人生の拠り所となるのですよ。という話でした。皆さんは、これからの人生において、いろんな競争に巻き込まれることがあると思います。また、いろんな挑戦をしていくことになると思います。うまくいくこともあれば、うまくいかないことも多いでしょう。勝つこともあれば、負けることも多くあります。それが人生を生きていくということだと思います。そんな人生の中で、決して忘れないでほしいことがあります。それは、常にひとと共に生きているという人生観・生き様の根本です。人を制圧するのではなく、人と共に生きるという温かい人間性を、どうか生き様の中心においてください。人とともに生きるという温かい人間性は、必ずや人のために尽くせる生き方につながると思っています。どんな勉強も、どんなスポーツも、そしてどんな仕事も、すべて人を幸せにするためにあるということを、決して忘れないでください。
皆さんのこれからの人生において、誰かを幸せにするために生きる。誰かの役に立つために生きる。誰かを救うために生きる生き様をどうか貫いてください。そして、人の幸せのために尽くせることこそが、自分自身の幸せと感じられる人になってください。
最後に、皆さんに伝えたいメッセージがあります。皆さんは「故郷に錦を飾る」という言葉をご存知ですか。将来、成功して、有名人になって、晴れがましい思いで故郷に帰るという意味です。よく、オリンピック選手や、何かに成功した有名人が、出身校に帰って、報告会や講演会を開くことがあります。「母校に錦を飾る」などと、マスコミは報道しています。私はこの卒業生の中に、将来、大きな夢を叶えて、本校に戻って講演をしてくれるような人が、出てきてほしいと願っています。でも、私が本当に願っていることは、「母校に心のよりどころ」を求めに戻ってきてほしいと思っています。皆さんが、将来、仕事に行き詰って疲れ果てたとき、人間関係で傷ついて悩んでしまったとき、大きな悲しみにうちひしがれたとき、どうしようもできないときこそ、母校に戻ってきてください。母校とは、いつまでも皆さんの心の風景に刻みこまれているはずです。自分が高校時代を過ごした校舎、体育館、グラウンド、校庭にきて、その時と同じ空気を吸ってみてください。同じ景色を見てください。きっと、高校時代の自分自身を思い出し、生きる力、前に歩む力が湧いてくることでしょう。疲れ悩み、苦しみの中にいるときこそ、心の風景に刻まれている母校にきて、空気を感じてください。景色をながめてください。きっと皆さんは心のよりどころを確認できて、そして一歩前に歩める力が得られるはずです。母校はそのためにあるものです。いつでも皆さんの心の風景のままでいますので、遠慮なく帰ってきてください。これが、私が皆さんに最後に伝えたいメッセージです。
それでは、卒業生の皆さん、気概をもって堂々たる人生を歩んでください。皆さんの限りない前途を祝福して、私の告辞といたします。
2019年3月2日
東海大学付属福岡高等学校 校長 津山憲司
『誇り高きサッカー乙女たちよ!』
校 長 津山 憲司
2019年1月7日夕刻、神戸ユニバ記念競技場、準決勝を戦い終えた本校のサッカー乙女たちがスタジアムから出てきました。一種清々しい表情の選手たちは、待ち受けていた応援部員たちと抱き合い絡み合いながら、笑いが絶えない時間が続きました。先ほどまで、あんなに闘志をむき出しにして戦っていた選手が、乙女の姿に戻っていました。そこには、ある種心地よいやりきった感が漂っていました。全国第3位。胸には‘金と同じ’「銅」メダルをかけています。今回の快挙は、東海福岡の新たな歴史の1ページを刻み込んでくれたと思います。
全国大会で、サッカー乙女たちはどんな景色を見たのでしょうか。1回戦、初の全国大会1勝を挙げたとき、どんな景色だったでしょうか。ベスト8に入ったときの景色は。そしてベスト4に這い上がったときの景色は、どんなにすばらしかったでしょうか。大きなスタジアム・試合前の緊張感・ロッカールームの雰囲気・芝のにおい・そして張り裂けそうな応援の声とその想い。きっとベスト4に入ったチームにしか見られないすばらしい景色が広がったことでしょう。その景色を決して忘れないでください。そして、またすばらしい景色を見るために、未来にむかってそれぞれが歩んでいって欲しいと思います。
我々チーム東海福岡の生徒・教職員の全員が、皆さんが見た景色を一緒に想像できたと思っています。自分たちの仲間が全国3位になったことは全員の誇りです。全員に、「自分たちも全国トップをめざし、できるんだ!」という勇気と希望を与えてもらえました。チーム東海福岡全員が、それぞれのNO.1をめざしてがんばれる力をもらったと思っています。本当にありがとうございました。
最後に、女子サッカーの皆さんは、普段からグラウンド内でもあるいはグラウンドの外でも、いつもすばらしい行動・立ち振る舞いでありました。練習中の取組み・練習準備や道具の運搬、挨拶・清掃そして笑顔。どれをとっても全国トップレベルでした。ですので、今回の全国ベスト4は本物であり、本当に心から応援したいチームでありました。そして、まさに“誇り高きサッカー乙女たち”でありました。
全国選手権大会第3位、おめでとう! そしてありがとう!