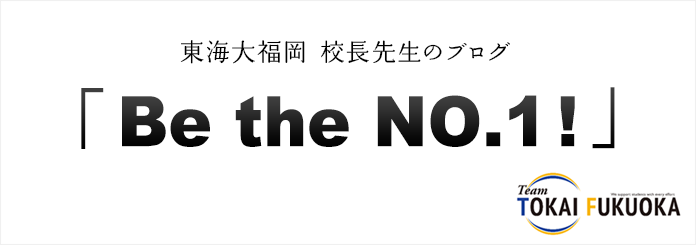
2019年新年メッセージ 『進化』 校長 津山憲司
明けましておめでとうございます。
2019年(平成31年)がスタートしました。今年は「平成」最後の年となります。新たに元号が改められ、まさに新しい時代に変わっていこうとしています。現在の社会情勢は、SNSの普及やAI(人工知能)・IOT(モノのインターネット化)などの社会進出によって、どんどん変化していこうとしています。いや、変化ではなく「進化」を遂げようとしているのかもしれません。そういった社会情勢の中で、我々の価値観や考え方も変わっていかなければなりません。古い慣習や価値観から、勇気をもって新しい考え方に挑戦していかねばなりません。それが「パラダイムチェンジ」(今までの価値観や考え方を劇的にチェンジすること)ということです。
本校が進化するために、私が本校の生徒の皆さんや教職員に望むことは、「主体性」だと思っています。第35代アメリカ合衆国大統領ジョン・F・ケネディの就任演説の中で有名な一説があります。「国があなたのために何をしてくれるではなく、あなたが国のために何ができるのかを考えようではありませんか」と述べ、さらに「私たちは、今までになかったものを夢見る人々を必要としている」と訴えています。今の時代にこそ重要な意味があると思います。誤解を恐れずに言うと、「学校があなたに何をしてくれるのではなく、あなたが学校に何ができるのか」・「授業があなたに何をしてくれるのではなく、あなたが授業にどうかかわっていけるのか」・「チームがあなたに何をしてくれるのではなく、あなたがチームのためにどんな貢献ができるのか」を強く考えてほしいと思っています。
本校のスローガン「Team Tokai Fukuoka」、本校は「グループ」ではなく「チーム」です。「グループ」とは単なる人の集団を意味しますが、「チーム」はある目的のために目標にむかって進む集団を意味します。ですので、「仲良しグループ」とは言っても、「仲良しチーム」とは言いません。また、「強い絆で結ばれたチーム」と言っても、「強い絆のグループ」とは言いません。本校は「チーム」です。「高い人間力をつける」という目的のために、授業や部活動、イベントなどにおいてそれぞれの目標にむかって進む「チーム」なのです。
今年は授業改革2年目です。また、部活動改革や教員の働き方改革にも着手しようとしています。「チームがあなたに何をしてくれるのではなく、あなたがチームのために何ができるのか」という「パラダイムチェンジ」することこそが、皆さん一人ひとりの「進化」に繋がっていくと信じています。
2019年が、皆様方にとって健康で明るい年になることを、また「進化」する年になるように願っています。
最後に、女子サッカー部の皆さん、明後日からの全国選手権大会での健闘を大いに期待しています。頑張れ!
『あっぱれ! 「なでしこTokai Fukuoka」』
本校の女子サッカー部が、冬の全国選手権大会出場を懸けて沖縄で行われた女子サッカー九州大会を戦いました。結果は3位となりました。
金と同じ値打ちの見事な銅メダルです。その大会の中でも、特に大分県代表の柳ヶ浦高校との準々決勝は、全国大会を懸けた大一番であり、お互いに気持ちが前面に出た一歩もひかない好ゲームでありました。両チームの攻防を見ている誰もが手に汗握る試合でありました。結果1対0で競り勝ち、全国女子サッカー選手権大会に2年連続3度目の出場を決めてくれました。チーム全員で勝ち取った勝利であります。本当によくやったと思います。
全国大会出場を勝ちとることのできるチームはほんの一握りです。多くのチームや高校は、一歩手前で残念にも夢破れてしまいます。だからこそ、今回の出場権を懸けた試合は、なによりも重く価値ある勝利だったと思います。女子サッカー部のみなさん、本当におめでとうございます。
私が応援のため沖縄に入ったのが、準々決勝の試合当日の朝でした。すぐに試合会場に到着すると、今回の女子サッカーの遠征をお手伝いしていただいているラド観光の原田さんから、こんな話を伺いました。「チームが沖縄入りした翌日、ある総合運動公園陸上競技場を借りて試合前日の練習をした際に、その競技場の管理責任者の方からお褒めの言葉をいただきました。『こんな気持ちのいいチームは初めてです。グラウンド準備の手際の良さ、練習後の後片付けも非常にスムーズ。何よりみんな立ち止まって気持ちのよい挨拶が最高です。本当に素晴らしいチームです。ぜひ頑張ってください。』と。」
これが勝利の秘訣であり、勝利する者の値打ちだと思います。関わっていただいたすべての方から応援されるチームなんだと思いました。このことは、一朝一夕に備わることではありません。来る日も来る日も気持ちのスイッチを入れて練習を重ねボールを蹴り続けることで、ようやくその成果が試合に出るのと同じです。日々の行動、日々の挨拶、一つひとつ言動の積み重ねが、自然と立ち振る舞いに擦り込まれる。そしてそのことが、今回のお褒めの言葉に繋がったのだと思います。
さあ、来年お正月の全国大会まで、グラウンドでの準備はもちろんですが、グラウンド外での準備も怠ることなく重ねて、全国大会まずは初勝利を期待しています。また、皆さんの気持ちのよい行動や挨拶は、本校の他の部活動やたくさんの生徒たちもできていることです。要するに、チーム東海福岡全体の行動、挨拶であるともいえます。皆さんが褒められることは、チーム東海福岡が褒められることでもあります。そういった意味でも、皆さんがチーム東海大福岡の代表として、全国のステージのグラウンド内外で、大いに活躍してほしいと願っています。
あっぱれ! 「なでしこTokai Fukuoka!」 よくやった!
東海大福岡の『敗れざる者たちへ』
〜“真に敗れていない君たちへ”のメッセージ〜
校長 津山 憲司
どんなスポーツにおいても、必ず選手としての引退の時がくる。高校における部活動では、なおさら突然で残酷な引退の時が毎年やってくる。2年と数ヶ月、自分の青春をかけて、朝早くから夜遅くまで打ち込んできた。甲子園、国立競技場、花園、日本武道館、、、福岡でナンバーワン、九州でナンバーワン、全国制覇。それぞれのナンバーワンを目指し、本当に日々努力を重ねてきたと思う。
しかし、多くの高校生は目標に届かず、夢半ばにして敗れていく。しかも試合に出られた者はまだ幸いかもしれない。スタンドで必死に応援をして高校スポーツを終えた者も少なくはない。高校スポーツは一度きりである。もう一度やりたい、もう一度甲子園へチャレンジしたいと願っても、卒業すれば二度とチャンスはやってこない。だからこそ、高校スポーツは美しく尊いのかもしれない。それだけではない。皆さんが必死にやってきた日々って、かけがえのない大きな意味がある。周りの仲間にとって、後輩たちにとって、指導者にとって、応援するすべての人にとって、皆さんの家族にとって。そして何より自分自身にとって大きくて深い意味がある。負けて悔しくてどうしようもないこと。できることならもう一度あの瞬間に戻りたいなどと、叶わないことを心で願ってしまうこと。すべてかけがえのない貴い意味がある。
では、かけがえのない貴い意味ってどんな意味なのか。
実はね、その意味を探すことこそが、皆さんにとってこれからの人生において大きな意味があると思う。現在の競技をさらに極めることも意味があるだろう。また別の世界で新たに勝負することも意味があるだろう。また、はっきりとしたステージは見えないけれど、その意味を探して彷徨うこともよしかもしれない。私の経験から言えることは、人生において、うまくいくことよりうまくいかないことの方がはるかに多いように思う。勝つことより負けてしまうことの方が多い。いや、実は人生は負けることの連続なのかもしれない。でもね、どんなに悔しくとも、どんなに辛くとも、どんなに苦しくとも、明日はまた必ずやってくる。どんなに辛くとも、訪れた明日を必死にもがきつづけなければならない。言い換えれば、明日に向かってもがきつづけることができていれば、まだ真に敗れていないということだ。
今回のテーマ『敗れざる者たちへ』は、明日に向かってもがきつづける、そんなまだ真に負けていない君たちに対するメッセージ。もがきつづける限り、真に敗れてなどいない。
東海大福岡の『敗れざる者たち』よ、どんなに辛くても必死にもがきつづけよ!
そして、いつか人生での真の勝利を勝ちとれ!
ガンバレ! Team Tokai Fukuoka
猛暑が続いていますが、みなさん元気に頑張っていますか。
私は、先日女子バスケットボールのインターハイの応援で名古屋にいて気温40度越えを経験しました。
まだまだ残暑が続きます。健康に充分に留意してください。
さて、インターハイの結果が出てきました。女子サッカー部は、残念ながら初戦の日ノ本高校に惜敗をしました。本チーム公式戦初の黒星でした。初めて部員たちの悔し涙を見ました。対戦相手の日ノ本高校は、インターハイ6回出場中5回優勝という超強豪校でした。今回の大会も準優勝でした。逆に言えば、本校女子サッカー部にとって、全国の頂点を経験できた貴重な大会だったのではないでしょうか。冬の全国選手権に向けて、今度こそ全国の頂点を目指し、さらなる飛躍を期待しています。
女子バスケットボール部は、日本で一番暑い愛知県で、熱い闘いをしてくれました。初戦の名古屋女子高校に見事な逆転勝ち。本当に素晴らしい試合でした。2回戦の東京成徳大高校には敗れたものの、全国大会で勝利した経験は、冬の全国選手権に向けてまた本チームにとって大きな財産になることでしょう。
陸上競技大会では、女子1500Mでは残念ながら決勝進出はなりませんでした。藤岡さんは来年またチャレンジしてほしいと思います。女子3000Mでは、菅田さんが1500Mでの悔しさを晴らし、決勝進出を決めてくれました。レースが終わり、菅田さんが応援に駆けつけた部員と対面した第一声が「みんなのお陰で勝てました!」という感謝の言葉でした。
本当に素晴らしく清々しい気持ちが伝わりました。また、男子5000Mでは、キムンゲサイモン君が決勝で見事4位入賞を果たしてくれました。おめでとうございます。北部九州大会では、後半失墜して悔しい思いをしていたと聞いていました。その雪辱を晴らせたことと思います。冬の全国駅伝大会を期待したいと思います。
もう一つ、素晴らしいニュースが入ってきました。吹奏楽部が福岡県コンクールで銀賞に輝き、九州吹奏楽コンクールへの出場が決定しました。なんと九州吹奏楽コンクールは創部以来初出場だそうです。昨年の地区大会突破からの1年で九州に抜けたという快挙です。昨年、福岡県コンクールへの出場が決まった際にこのブログでも書かせてもらいましたが、7年前わずか19名の部員での魂のこもった堂々たる演奏。そこが徳永吹奏楽部の原点であったと思います。さあ、九州コンクールでも、その原点を忘れないように、魂のこもった演奏を聴かせてほしいと思います。
今日から学園オリンピックも始まりました。9日には柔道部田中陸君のチャレンジが始まります。全生徒一人ひとりが、それぞれの熱い夏をどうか自らの強い意思で乗り越えてください。Team Tokai Fukuoka! ガンバレ!
『この夏のチャレンジ~ 仲間を信じ、己を信じ、一歩前に出よ!』
校長 津山憲司
この夏休み、部活動や補習そして望星丸研修・マレーシア研修など、それぞれのチャレンジがすでに始まっています。
望星丸研修は先日無事戻ってきました。望星丸での2泊3日の貴重な海上体験がたくさんできたのではないでしょうか。
マレーシア研修では、今週末ホームステイに入ります。マレーシアの家庭での様々な体験を通して、文化や習慣の違いを実感してほしいと思います。何事にも積極的にトライしてください。
さて、ラグビー部が先週末、ビッグな結果を残してくれました。全国高校7人制ラグビー大会で全国6位という結果を収めました。7人制ラグビーはオリンピック競技にもなっており、15人制と同じ大きさのピッチで繰り広げられるスピード感あふれるラグビー競技です。
全国の屈指の強豪校・伝統校と渡り合っての6位という結果は、本当によくやったと思います。この結果を自信に変えて、秋の花園大会の予選にむけて、ぜひ弾みをつけてほしいと思います。
吹奏楽部が、福岡支部コンクールで金賞に輝き、2年連続福岡県コンクールへの出場を決めてくれました。特に『カヴァレリア・ルスティカーナ』という自由曲は、優しいメロディー・早いテンポ、ソロの演奏・合唱、そしてダイナミックな演奏と、音楽素人の私が聞いていても、鳥肌の立つすばらしい演奏でした。県のコンクールでこの演奏ができれば、きっと次のステージ(九州コンクール)へも進出できるのではないかと思っています。普段、周りに音楽を通して笑顔と勇気を贈り続けている吹奏楽部の皆さん、今回はチーム東海福岡全体が皆さんにエールを贈っています。次のカテゴリーへチャレンジ、ぜひ頑張ってください。
8月に入りますと、いよいよインターハイが始まります。1日に女子サッカー部が初戦を迎えます。2日には女子バスケットボール部が、そして、陸上競技の3名・柔道の個人戦、それぞれのチャレンジが始まります。6日からは学園オリンピックで熱い闘いが繰り広げられます。ぜひ、ナンバー1をめざし、日頃の力を充分に発揮してほしいと思います。
今年の夏は猛暑がまだまだ続きそうです。しっかり水分・栄養を補給し身体に気をつけて、部活動に勉強に様々な活動に大いにチャレンジをしてください。
『さあ、仲間を信じ、自分自身を信じて、一歩前に出よ!』
アクティブラーニングで学校が変わる!
校長 津山 憲司
本校では本年度よりアクティブラーニングを全校的・組織的に推進し、生徒が積極的・能動的・協働的に参加できる授業を目指しています。そのために、アクティブラーニングを通して育てたい力を、社会で活躍するための能力資質=‘コンピテンシー’と定義しています。本校ではそれを「七つの学力」として明確化しています。「七つの学力」とは、知識技能獲得力・思考創造力・問題解決力・コミュニケーション力・チャレンジ力・チーム力・異文化理解力の七つです。その「七つの学力」を生徒に身につけさせるための授業展開がアクティブラーニングということです。ですので、授業の冒頭で、この時間は特にどの力をつけてほしいのかという本時の目標を教員は明示し、生徒と共有してから授業を始めることにしています。
また、教員組織の中にアクティブラーニング委員会を設けて、各教科から3名ずつの教員にアクティブラーニング委員になってもらっています。5月にアクティブラーニング委員の中での研究授業週間を行い、6月の2週目には教科ごとの研究授業週間を行いました。そして、本日6時間目に7クラスで、7教科の研究授業を行い、授業者8名(英語2名)以外の全教員が授業見学し、アクティブラーニングを研修する機会を設けました。7教科とは、5教科と保健、そして情報(情報・音楽・家庭科で1グループ)です。8名の教員が、アクティブラーニング研究授業にチャレンジをしました。プロジェクタ―を活用し教材の見える化をしたり、ペアーワークやグループワーク、ディベート形式等で生徒同士話し合わせたり、ミニ実験を試みたり、様々な工夫を用いた授業を展開していました。
私はアクティブラーニングを導入することで、教員が確実に変わってきたと感じています。授業でいかに生徒に考えさせるか、生徒が授業に参加するようにするにはどうすればいいか、などを真剣に悩んで考えています。また、教員同士がアクティブラーニングのことで話し合い、意見を交換し合える雰囲気も確実に多くなってきています。その影響で、生徒たちの授業への取組み関心度が増したとも感じています。アクティブラーニングの狙いは、生徒がいかに積極的に授業に参加し、しっかり考えて自分の意見を持ち、それを表現できるかがポイントです。生徒が変わってくれれば、アクティブラーニングは成功です。
あるアクティブ委員の先生のコメントです。「私は、アクティブラーニングを意識して、自分の指導方法がめちゃめちゃ変わりました。以前は、生徒から『なぜ化学を学ばないとならないの?』と尋ねられたら、『社会に出て必要だからだよ。』としか答えられませんでした。しかし、実際は、社会の中で化学の知識が必要な場面ってあまりないのです。でも、今はそんな質問に対し、『七つの学力のうちこういう力をつけるために、(たとえば)化学反応の勉強は必要なんだよ。』と自信をもって答えることができるようになりました。また、アクティブラーニングを意識するようになって、部活の指導も変わりました。以前は過程も結果も言ってましたが、今は、過程か結果のどちらかを伝え、もう一方は選手自身に考えさせるように心がけてるようになりました。」
今、確実に東海大福岡のアクティブラーニングで、教師が変わり、指導の考え方が変わり、授業が変わり、生徒たちが変わってきています。そして、学校が変わろうとしています。ぜひ、これからの取組みに期待してください。
全国の舞台で掴みとれ!
津山 憲司
一昨日は、サッカー日本代表がワールドカップ初戦にて、コロンビアに歴史的勝利をし、日本中が沸き立ちました。ぜひ、予選リーグを突破して決勝トーナメントに進出してほしいと思います。
サッカー日本代表の勝利の前日、本校女子サッカー部が全国高校総体九州大会において見事優勝し、九州女王となり、高校総体(インターハイ)出場を決めてくれました。新チーム結成以来公式戦負けなしの24連勝ということです。しかし、苦しい試合もたくさん乗り越えてきたと思います。特にインターハイ出場を賭けた準決勝の長崎鎮西高校戦では、延長後半アディショナルタイムでの決勝ゴール。実力も運も掴みとっての大きな勝利だったと思います。インターハイでも、ぜひ日本一という栄冠を掴みとってきてほしいと期待しています。
また、ラグビー部が7人制ラグビー全国高校大会に初出場を決めてくれました。福岡県大会決勝では前年度全国優勝の東福岡高校にあとワントライ差まで詰め寄りましたが、最後は離され準優勝となりました。しかしながら、トンガからの留学生も大活躍をして掴みとった出場権でした。全国大会では少しでも高みに登れるように頑張ってください。
この夏、インターハイに出場する部活動は、女子サッカー部・女子バスケット部・男子陸上部の3年キムンゲ・サイモン君・女子駅伝部の3年菅田雅香さん1年藤岡加梨さん、そして柔道部の3年田中陸君です。そして、7人制ラグビー全国高校大会にラグビー部が出場します。また、全国高校総合文化祭の詩吟剣詩舞部門で3年金子楓さんが出場し、2年の井上紗希さんが全日本空手道選手権大会の出場も決まっています。
皆さん、あと1カ月、しっかり準備して、全国の舞台で大きなチャレンジをしてください。健闘を祈っています。“Team Tokai Fukuokaは皆さんの頑張りを応援しています!”
『インターハイ出場よくやった! そして続け!』
校長 津山憲司
女子バスケットボール部が、2年ぶり3回目のインターハイ出場を決めてくれました。本当によくやりました。たいへん嬉しく思います。地区大会から苦しい試合も多かったと聞いています。何試合もの接戦を制してのインターハイ出場権獲得でした。おめでとうございます。インターハイまであと2ヶ月、その前に九州大会、またたくさんの経験を積んで、もっともっとチーム力を上げてインターハイに臨んでください。
また、女子バスケの部員たちは、毎朝早くから校庭を清掃してくれています。朝8時ごろには、校庭に落ちていた葉っぱもきれいにはばいてくれています。本当に頭が下がります。しかも、やらされている感じが全くしないのです。自分たちの当たり前の仕事のごとく黙々と清掃活動をしてくれます。私はそのあたりに強さの秘訣があるのだと思っています。先日、掃除をしてくれている女子バスケの生徒3名ほどが、しゃがんで道路の何かを手でとっていました。私は近づいて彼女たちが何をしているのか見てみると、なんと地面のひび割れた部分に生えている草をむしってくれていました。なんとそんな細部にまで目配り気配りができている生徒たちか。驚きと感動と感謝でいっぱいになりました。以前に講演してくれた岡田元サッカー日本代表監督の言葉を思い出しました。『勝利の神様は細部に宿る』インターハイでの活躍を期待したいと思います。
柔道部の田中陸君が60キロ級個人戦で優勝し、インターハイ出場を決めてくれました。団体戦では悔しい思いをしましたが、よく雪辱を果たしてくれました。軽量級はなにしろ激戦と聞いていました。その激戦を制して見事な優勝です。これからも精進を重ねてインターハイに臨んでください。一層の活躍を期待しています。
そのほか、女子サッカー部が福岡県大会で優勝をしました。決勝戦では新生の筑陽学園を退けての優勝でした。2枚のインターハイ出場キップを争っての九州大会。インターハイ出場を必ずや決めてくれると思っています。なにしろ女子サッカー部は新チームになって公式戦全勝。とにかく強いです。決して油断や緩みがないようにして、インターハイで真の強さを身につけてほしいと願っています。また、男女陸上の多くの選手たちが、インターハイを懸けた北部九州大会に臨みます。そして、今週ラグビー部も七人制全国大会を懸けた決勝トーナメントに臨みます。ぜひ頑張ってほしいと思います。
最後に、先週の土曜日、男子サッカー部が準決勝で東福岡高校に延長戦の末惜敗をしました。私も観戦してましたが、気迫のこもった好ゲームでした。いや気迫では完全に優っていたと思っています。今は王者の東福岡をもう一歩のところまで追いつめました。感動しました。秋の選手権大会は、絶対に自分たちが勝つと信じて頑張ってください。全国行こうぜ!
『Team Tokai Fukuoka』総力戦で闘おう!
『Kingdom of Tonga 紀行』
〜後編「人生出会いを大切に!」〜
校長 津山 憲司
最終日午前中、留学生との家族と面会を終えたあと、ヌクアロファの港から船で15分ほどの離島に行くことになりました。船といっても 20名くらいで満杯になる小舟です。離島では、軽食やジュースなどがおいてある小さな小屋以外なにもありません。
そこにあるのは、青い海と青い空、そしてきれいなビーチのみです。少しの時間ですが、南の島の素晴らしさを味わうことができました。再びヌクアロファに戻り、バイタさん(U18トンガ代表監督)と打合せ。来年度、U16トンガ代表が日本遠征を計画しており、本校と繋がっている縁から福岡へ遠征に行きたいということでした。バイタさんという方は、U18トンガ代表監督でありますが、実はトンガ政府の高官をされています。今後、トンガと日本の友好に少しでも貢献できればと思い、できる限りの協力を約束してきました。夕食は、バイタさんに地元のトンガ料理の店に連れて行ってもらいました。そこで、初めて子豚の丸焼きをいただきました。本校の3名の留学生から聞いてはいたのですが、見るのも食べるのも初めての経験でした。少しかわいそうな気持ちになりましたが、たいへん美味しくいただきました。何か、普段の食べる豚肉とは違い、命をいただいているという感覚がいたしました。日本でも店に並んでいるパックのお肉でなく、時にはこのような命の姿が見えるような機会も必要ではないかと感じました。「ごちそうさまでした」。
夜にヌクアロファ空港を飛び立ち、夜中にニュージーランドのオークランドに戻ってきました。翌早朝、オークランド市街が一望できる丘に登りました。あいにくの天気で、雨が強く降ったり、ピタッと止んだりと、この季節ニュージーランド特有の天気だそうです。頂上に着くと、今まで見たことのない光景を目にすることになりました。奇跡的に雨が上がり、朝陽が昇ってきました。するとなんと、オークランドの街を包むような虹がくっきりとあらわれました。そしてそのうち虹が二重のラインとなって、オークランドを包んでいます。本当に神々しい光景でした。しかも、虹が海から飛び出しているところもくっきり見えています。昔から、虹の根元には夢が埋まっていると言われています。その光景を目にすることができて、『東海福岡の夢への挑戦』もしっかり捉えられたように感じました。
今回のトンガ王国への旅は、実質3日間の体験でしたが、中身の濃い旅となりました。2つの大きなミッションもうまく進み、それだけではなく今後の出会いや縁に繋がるきっかけも得られたような気がします。旅は出会いの連続です。出会った人との縁をしっかりと繋げられるかどうかは、自分自身のこれからの志(こころざし)次第であると思っています。誰しも出会いのチャンスは平等にあるものです。そのチャンス(運)を縁に繋げられるかどうかで、その人の人生の豊かさに関係してくるのだと思います。古より“人生は旅”と申します。まさしく、“人生は出会い”です。出会った人との関係を大切にして、また何かの縁に繋げていく。これが、人生を豊かにするヒントだと私は思っています。さて、生徒の皆さんも、東海福岡高校で出会った縁を大切にして、これからの人生を豊かなものにして欲しいものです。生徒の皆さんだけではなく、チーム東海に関わっていただいているすべての方々にこのメッセージをお伝えして、今回の紀行文、ペンをおきたいと思います。
どうか、皆さんが自分のそれぞれの夢を掘りだして、この世の中に素晴らしい虹をかけてくれることを願っています。 ・・・おしまい
『Kingdom of Tonga 紀行』
〜本編「ミッションと母親の想い」〜
校長 津山 憲司
トンガ王国の首都ヌクアロファ空港に到着し、無事にトンガ王国に入国できました。トンガ王国の人は「ガリバー旅行記」のモデルになったといわれているほど、とにかく大柄な人が多いです。男性も女性も100キロ超は当たり前、お相撲さんのような人がたくさんいます。人柄はたいへんフレンドリーで、街で歩いていると出会う人出会う人が、笑顔で「Hey!」と挨拶をしてくれます。体も心もおおらかな人たちです。また、トンガの衣装で正装するときは、腰に「Taʻovala」という相撲のまわしのようなものをつけています。政府の役人も空港の職員も学校の先生も生徒も、みんな腰にトラディショナルな「Taʻovala」をつけています。そんなところにオリジナルな文化と風習を感じます。その文化はいつまでも大切に守って欲しいものです。ヌクアロファの街は、高い建物もなく交通量も少なくのんびりとしたところです。目立つ建物は、王宮と王様のお墓、そして教会です。政府機関の建物もせいぜい3階建ての高さで、人の大きさに反比例してこじんまりとした街です。街の中心部には大きなマーケットがあります。サンリブやゆめタウンのようなイメージではなく、昔の商店街・市場のような感じです。野菜を売っているおばさんもたいへんフレンドリーでした。私にとっては、懐かしい心温まるマーケットでした。
さて、今回のミッションの第一の目的であるスカウトが始まりました。15歳と16歳のラグビーの試合を観に行きました。あらかじめトンガU18代表監督であるバイタさんとうい人に、U15・U16トンガ代表選手の中で、日本でやっていけそうな資質と性格と技量の選手を、数名候補にあげてもらっています。東海大学というスケールメリットを使って、バイタさんという大きな味方をつけて、このミッションは成り立っています。現在在籍している3名も同じくバイタさんの一押しの選手たちでした。
試合は、トンガU15・U16大会の準々決勝が行われていました。その中で、トンガハイスクールのヴィリアム君という180センチ94キロのパンチ力のある選手と交渉をすることにしました。試合後、ヴィリアム君とそのお父様に話を聞いてもらいました。いい感触をつかめました。そして翌日には快諾のお返事をもらいました。第一ミッションSuccessです!ヴィリアム君の通っているトンガハイスクールはトンガで一番成績の優秀な学校で、現在本校1年生のシアレも同じ学校です。二人とも実にクレバーな子供です。もちろん現在2年生のフィナもポロも優秀でクレバーですよ(笑)。とにかく、来年日本に来てくれるということで、今回のミッションの一つは大成功です。
トンガの少年ラグビーの試合は、本当に激しいものでした。ラグビーの攻撃の手段として、ボールを持ったらパスをするか、キックをするか、自分走るか(ラン)の三つの選択肢があります。トンガの選手はボールを持ったらとにかくランします。そして、デフェンスの選手にぶつかっていきます。15・16歳の試合でも非常に激しいぶつかり合いです。日本の高校ラグビー(18歳)よりも激しい試合でした。トンガの試合を観て二つの面白いことに気がつきました。一つ目は、タッチフラッグ(タッチジャッジの持っている旗とコーナーポストに立てている旗)が、なんと木の枝でした(写真参照)。まさにローカルなシステムです。もう一つは、応援している母親の熱狂ぶりが日本と同じ、いや日本以上の盛り上がりでした。トライのあとは、踊り出す母親や、グラウンドの中に入っていきそうなくらい熱狂した応援ぶりでした。母親の息子の活躍を喜ぶ気持ちは万国共通ですね。
翌朝、本校の留学生3名の家族がホテルまで私に会いに来てくれました。日本での学校生活・寮生活やラグビーの成長ぶりなどたくさん話をしました。ラグビー部コーチの林英輝先生が作成した3名の映像(試合のプレーダイジェスト、寮生活、家族へのメッセージ)を見て、母親はタオルを出して泣きながらじっと見ていました。私も本当に目頭が熱くなりました。子を想う母親の気持ちはどこの国も関係なく本当に尊いものです。また我々教職員は、そんな家族の想いをしっかりと受けとめて子どもたちを育てないとならないと、改めて心に強く感じたことでした。最後に、2年のフィナ君のお母さんは涙が乾いたあと、フィナの学習成績表を送ってほしいと頼まれました。また成績がよくなければ、母親がトンガからテキストをどっさり送るということでした(笑)。どの国の母親も全く思いは同じです。フィナ君、覚悟をしておきなさいよ(笑)。
なにはともあれ、二つの大きなミッションを無事終えることができました。これも、大学の木村監督と石黒コーディネータおよびバイタさん、そしてすべての関係者の方々のおかげです。本当にありがとうござました。家族との面会を終えたあと、オークランドに戻る夜のフライトまで、船で15分ほどの離島に連れて行ってくれました。たいへん美しい海が見られました。そして、トンガをあとにして、夜中にオークランドに到着し、翌日に日本に戻ることになりました。そのときの紀行は後編でお伝えしたいと思います。つづく・・・

























